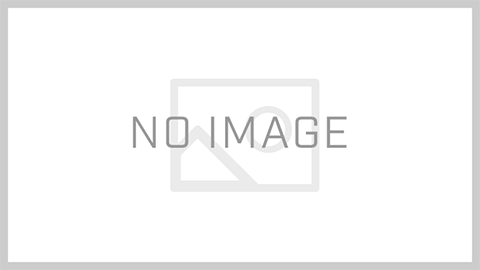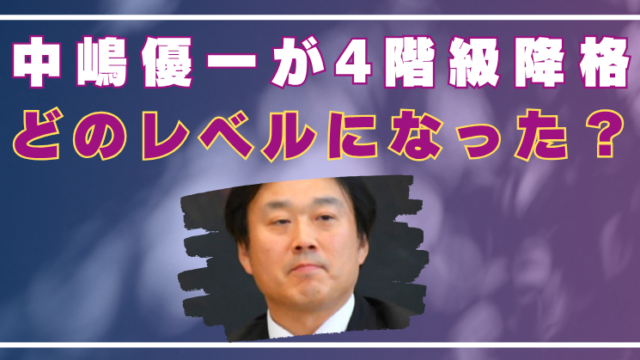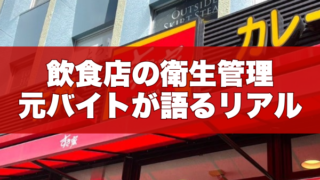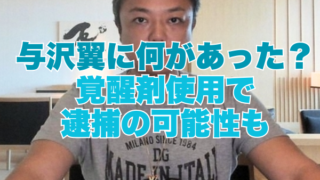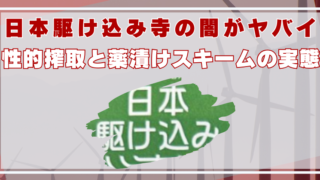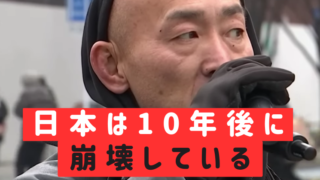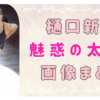すき家の異物混入は小林製薬紅麹と同じ?何者かが仕掛けた陰謀説
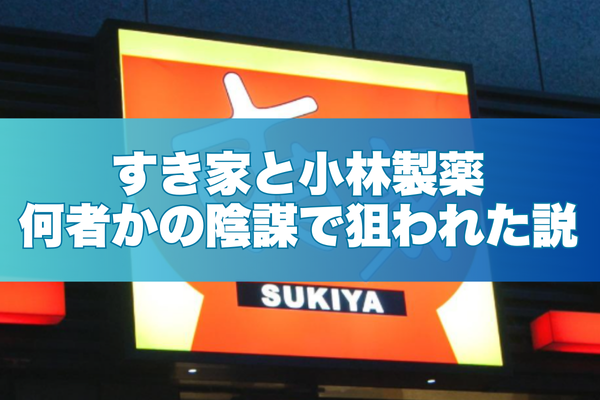
2025年、牛丼チェーン「すき家」が異例の全店一時閉店を発表しました。
発端は、1月に発覚した“味噌汁へのネズミ混入”、そして3月の“ゴキブリ混入”という立て続けの異物混入。
ゼンショーによる衛生対策の徹底と再発防止策の一環とはいえ、SNSでは「何か裏があるのでは?」という声が相次いでいます。
そんな中、2024年に話題を呼んだ小林製薬の紅麹サプリ問題と重ねるように、「すき家も何か仕掛けられたのでは?」という見方も浮上。
国産米100%にこだわる企業姿勢、タイミングの一致、そして曖昧な発表内容──
表には出ない“もうひとつのシナリオ”を、冷静にひもといていきます。
すき家の異物混入に陰謀論
2025年、すき家が予想外の事態に見舞われました。
1月には鳥取県の「すき家 鳥取南吉方店」で、味噌汁にネズミが混入。
3月には今度は東京都昭島市の店舗で、ゴキブリの一部が料理に混ざっていたと発表されました。
そして、すき家を運営するゼンショーホールディングスは、3月31日から4月4日まで、ショッピングモール内の一部を除く全国約1970店舗を一時閉店するという異例の措置を発表。
「害虫・害獣対策と衛生管理の徹底」を目的に、清掃と点検が行われるとされています。
ゼンショーは原因を「従業員の目視確認不足」「衛生管理の不徹底」と説明しましたが、肝心の混入経路や現場での具体的な状況については明らかにしていません。
この不透明さが、SNS(特にX)上で憶測や疑問を呼び、
- 「2件連続で発覚するって偶然にしては不自然では?」
- 「拡散スピードが異常すぎる、誰か仕掛けた?」
といった“陰謀論的”な声が広がるきっかけにもなっています。
実際、どちらのケースも、発覚からSNSでの拡散までが非常に速く、「本当に一般の投稿だけでここまでの広がりを見せたのか?」と疑うユーザーも。
加えて、どちらの事件も混入の“具体的な状況”が曖昧なまま。
ネズミは「具材準備の段階で混入した可能性」とされ、ゴキブリは「一部が混入していた」としか明かされておらず、細かな調査結果は出ていません。
この“曖昧な公式見解”が、結果的に憶測を助長する構図になってしまっているようです。
すき家全店閉店は小林製薬紅麹と同じ?
このすき家の事例が、思わぬかたちで比較されているのが、2024年に起きた「小林製薬の紅麹サプリメント問題」です。
紅麹成分を含むサプリの摂取により健康被害が相次ぎ、製品回収と謝罪会見に発展。
原因は「未知の成分(プベルル酸が有力)」とされつつも、最終的な特定には至っていません。
両事件には、いくつかの共通点があると指摘されています。
- 短期間に発生した重大トラブル
- 公式発表が曖昧なまま「調査中」で止まっている
- SNS上での拡散が早く、メディア報道も加熱
- 経済的影響(株価下落など)への懸念が浮上
SNS上では、
- 「紅麹とすき家、流れが似すぎていて怖い」
- 「同じ手口で企業潰しにかかってるのでは?」
という見方も少なからず見られます。
ただし、現時点で両者の背後に“共通した外部要因”があるとする根拠はなく、あくまで構造的な類似性に基づく意見にとどまります。
それでも、
- 「公式がはっきり言わない」
- 「メディアも一部の視点しか報じない」
という点に“情報の不自然さ”を感じる人が出てくるのは、ごく自然な反応なのかもしれません。

その中でも、今回特に注目されているのが
- 「小林製薬=コロナ対策を邪魔された説」
- 「すき家=国産米潰し説」
が重なっている点です。
以前、SNSで「小林製薬はヨウ素系の研究でコロナに効く可能性を見出してた。それを潰すために紅麹が使われた」という説が流れました。
つまり、“紅麹はスケープゴートだったのでは?”という見方です。
これはもちろん公式には否定されていますが、背景説明が薄いこともあり、今も根強く信じる人が存在します。
他にも、「これって株価を下げて、外資に買い叩かれる流れを作ってるんじゃないか?」という声も一部聞こえます。
というのも、小林製薬の株価は実際に下落し、一時買収懸念もささやかれたからです。
すき家に関しても、「異物混入のダメージで信頼が落ちたタイミングを狙って、買収が狙われるのでは?」といった声が上がっています。
陰謀論と断ずるのは簡単ですが、
- 「なぜこのタイミングで2件続いたのか?」
- 「なぜ原因がはっきりと明かされないのか?」
- 「小林製薬と同じパターンじゃないのか?」
という“引っかかり”を感じる人が多いのです。
すき家は誰に狙われたのか?
すき家にまつわる陰謀説の中でも、注目を集めているのが「国産米」へのこだわりです。
すき家は、日本の牛丼チェーンの中でも珍しく、全店舗で国産米100%を使用しています。
(※吉野家は国産+外国産のブレンド、松屋は外国産米を採用)
一方、2024年産の米は価格が高騰し、前年に比べて約48%も値上がりしたと報じられました(農林水産省発表)。
この影響で、飲食業界では外国産米へのシフトが進みつつあります。
そんな中で、すき家の“国産米堅持”はある種のメッセージともいえます。

しかしそれが、アメリカ・オーストラリア・タイなどの米輸出国にとって“障壁”となっているという見方も存在します。
X上では、こうした投稿が出ています。
- 「すき家が国産米で踏ん張るから、外国産米の流通が広がらない」
- 「国産米を使う代表企業を潰せば、業界全体が外国米に切り替わるのでは?」
もちろん、これは“憶測”にすぎません。
現在、すき家に対して外国勢力が何らかの工作を行ったという証拠は確認されていません。
ただ、経済的動機という点で見ると
- 企業ブランドの低下
- 株価の下落
- 買収のチャンス
という“メリット”が発生する構図があるのは確かです。
しかも、メディアでは国産米の話や「買収リスク」にはあまり触れられていない。
報道は「ワンオペ」「衛生管理不足」といった“内部要因”に集中しています。
この偏りも、「何か触れてはいけない事情があるのでは?」という見方につながってしまっているようです。
一方、SNSでの拡散の速さに着目する声も。
- 「拡散があまりに速い」
- 「動画が即バズるのは工作員?」
といった憶測も出ています。
小林製薬の紅麹騒動でも、同様の情報操作が疑われた経緯がありました。
現代は、ひとつのツイートや写真で企業の評判が一変する時代。
多くの国民が政治に不満を抱き、生活に困窮を感じている中で、「仕組まれたように見える出来事」が立て続けに起きた──
これこそが、陰謀論を生んだ一番の要因になってしまっているのかもしれませんね。