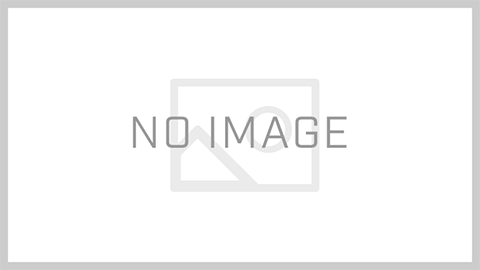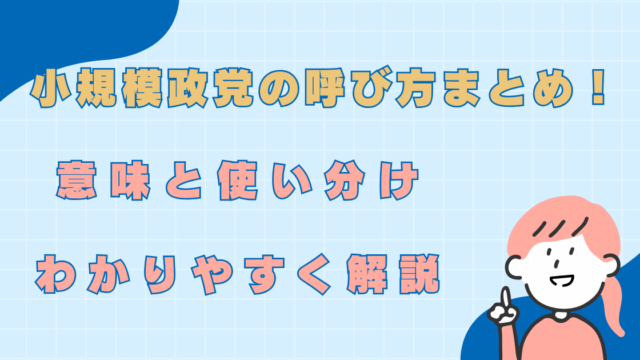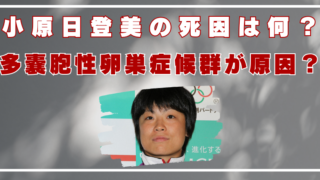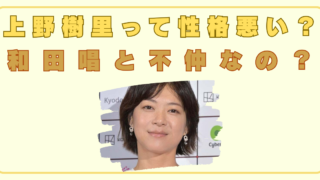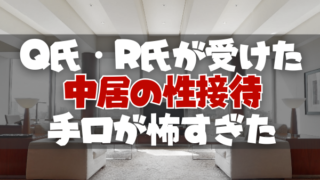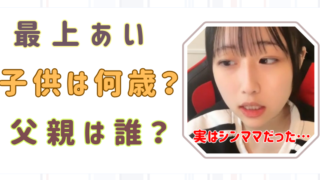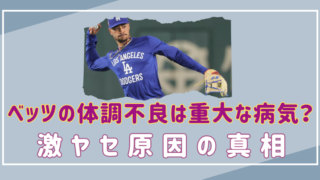衆議院と参議院の違いを子供向けに簡単にわかりやすく解説!

「衆議院(しゅうぎいん)」と「参議院(さんぎいん)」という言葉、社会の授業やニュースで聞いたことはあるけれど、「どう違うの?」と聞かれると、ちょっとむずかしく感じる人も多いかもしれません。
でも実は、この2つのちがいを知ることは、日本という国のルールの土台(どだい)を知ることにつながります。
この記事では、小学生や中学生でもすっと理解できるように、「学校」や「給食」など、身近なたとえを使って、衆議院と参議院のちがいをやさしく解説します。
なんのために2つあるのか?
どんなふうに議員が選ばれるのか?
そして、自分の生活にどんな影響があるのか?
読むうちに「政治って、意外と自分と関係があるんだな」と感じるはずです。
「まだ投票できないから関係ない」と思っている人にこそ、今こそ知っておいてほしい話です。
目次
衆議院と参議院ってなに?学校にたとえると…

政治の話って、なんだかむずかしそうに聞こえますよね。
でも、実は「学校」にたとえると、とてもわかりやすくなります。
たとえば、あなたの学校にも「クラス」と「学年」ってありますよね?
- クラスは、身近な友だちとすぐに話し合って、いろんなことを決める場所
- 学年は、もっと広いグループで、先生たちも入って、じっくりと考えてルールを見直す場所
この「クラス」と「学年」の関係に、ちょっと似ているのが
- 衆議院(しゅうぎいん):すぐに動ける、スピード優先のグループ
- 参議院(さんぎいん):ゆっくり考える、見直し担当のグループ
つまり、衆議院は「すばやく動くチーム」、参議院は「落ち着いて考えるチーム」なんです。
もし政治が衆議院だけだったらどうなるでしょう?
たとえば、みんなが「これやろう!」って盛り上がったときに、すぐに決めてしまって、あとから「やっぱりダメだった」となっても止められません。
でも参議院があることで、「ちょっと待って、それ本当に大丈夫?」とストップをかけることができます。
さらに、予算や外国との約束(条約)のときは、衆議院の意見が優先されるというルールもあります。
それぞれにちがう役割があるからこそ、日本の政治はかんたんに暴走(ぼうそう)しないしくみになっているのです。
議員の数や選び方がちがう理由とは?
衆議院と参議院には、「人数」や「選び方」にも大きなちがいがあります。
まず、人数です。
- 衆議院には 465人 の議員がいます
- 参議院には 248人 の議員がいます
これは、衆議院のほうが国民の声をすばやく集めて、すぐに動けるようにしているからです。
次に、議員の選び方。
衆議院では、
- 全国をいくつかの地域に分け、それぞれで1人を選ぶ「小選挙区(しょうせんきょく)」
- 政党の人気に応じて議席をわける「比例代表(ひれいだいひょう)」
この2つを組み合わせたしくみになっています。
参議院では、
- 都道府県ごとに選ぶ「選挙区」
- 全国で政党や候補者リストに投票する「比例代表」
という方式です。
たとえるなら、衆議院は「身近な代表と政党の人気」でバランスよく選び、参議院は「地域と全国の声のどちらも聞く」しくみ。
さらにもう一つ、議員になるための年齢もちがいます。
- 衆議院の議員になれるのは 25歳以上
- 参議院は 30歳以上
- どちらも投票できるのは 20歳以上の日本国民 です
この年齢のちがいも、「すぐ動ける人」と「じっくり考える人」という役割分担を表しています。
それぞれのしくみがあることで、「いろんな立場の意見」が国の政治に生かされているんですね。
参議院選挙の非改選って何?
「非改選(ひかいせん)」という言葉、ちょっと聞きなれないかもしれません。
でも、参議院のしくみを知るうえで、とても大切なキーワードなんです。
まず、「改選(かいせん)」とは、選挙で新しい議員を選び直すことを意味します。
つまり、「非改選」とは「今回は選び直さない議員」のことです。
参議院では、6年の任期を持つ議員が、3年ごとに半分ずつ入れ替わるようになっています。
だから、選挙のときに全員を選ぶわけではなく、半分の議員だけが対象になります。
残りの半分は「非改選」として、次の選挙までそのまま仕事を続けるのです。
たとえば、2025年の参議院選挙では、2019年に選ばれた議員の任期(6年)が終わるので、その人たちが改選の対象になります。
一方、2022年に選ばれた議員は任期がまだ3年残っているため、今回は選ばれません。
これが「非改選議員」です。
このしくみ、学校でたとえるとこうなります。
ある学校の学級委員(がっきゅういいん)は、6年間の任期で活動しています。
でも、クラスのルールや雰囲気が急に変わりすぎないように、3年ごとに半分だけを選び直します。
そうすると、新しいメンバーも入りつつ、前からいる委員がクラスを支えてくれる。
だからこそ、クラスの「安定」が保たれるんですね。
参議院もそれと同じで、政治の流れが急にガラッと変わらないように、非改選の議員が経験や知識を引き継ぎ、政治の急激な変化を防いでバランスを取っているのです。
さらに、参議院には解散がないという特徴もあります。
だからこそ、3年ごとの選挙と非改選のしくみがセットになっていて、安定した政治運営ができるようになっているのです。
この非改選の存在によって、与党(よとう)と野党(やとう)の力のバランスが急激に変わりにくくなり、政治が安定して進んでいくという効果もあります。
見えにくいしくみかもしれませんが、実はとても大切な「政治の土台」のひとつなんです。
衆議院だけにある「解散」ってなに?
選挙と聞くと、「決まった時期にやるもの」と思っていませんか?
でも、衆議院には『解散』というしくみがあるため、いつ選挙が行われるかわからないこともあるのです。
解散とは、「いったん全員をやめさせて、もう一度やり直そう!」ということ。
もっと正確に言えば、内閣が『国民の声を聞き直したい』と決めたときに、天皇が解散を宣言するというルールです。
たとえば、学校で係や委員をぜんぶリセットして、もう一度みんなで決め直すようなイメージ。
そのあとに、必ず新しいメンバーを選ぶ選挙が行われます。
一方で、参議院にはこの「解散」がありません。
議員の任期は6年で、3年ごとに半分だけが選び直されるしくみです。
これは、政治がバタバタしすぎないようにするため。
急にぜんぶが変わると、落ち着いて話し合うことができませんからね。
つまり、衆議院はスピード感のある「動きやすいチーム」、参議院はゆっくりと「安定したチーム」。
ちがう動きをすることで、日本の政治がバランスを保てるようになっているのです。
なぜ2つあるの?一つじゃダメなの?

「衆議院と参議院、2つも必要なの?」
そう思った人もいるかもしれません。
たしかに、国のことを決めるグループが1つだけなら、もっと早く物事が決まるかもしれません。
でも、それって本当にいいことなのでしょうか?
たとえば、クラスで「明日から毎日カレーにしよう!」って、勢いだけで決めたとします。
アレルギーのある子や、苦手な人の意見はどうなるでしょう?
政治も同じで、スピードだけでは足りません。
大切なのは『じっくり考えてチェックすること』です。
だからこそ、衆議院の決定に対して、参議院が「ちょっと待って!」と止める役割を持っているんです。
参議院が「NO」と言ったら、衆議院が3分の2以上の特別な多数で再投票しないと、その決定は止まることもあります。
一方で、予算や外国との約束(条約)、内閣総理大臣の指名などについては、衆議院のほうが優先されるルールがあり、最終的には衆議院が再び投票して決めることもできます。
このように、すばやく進めるチームと、じっくり見直すチームがあるからこそ、
かたよらずに、安定した政治ができているのです。
自分に関係ない?じつは日常にかくれた影響
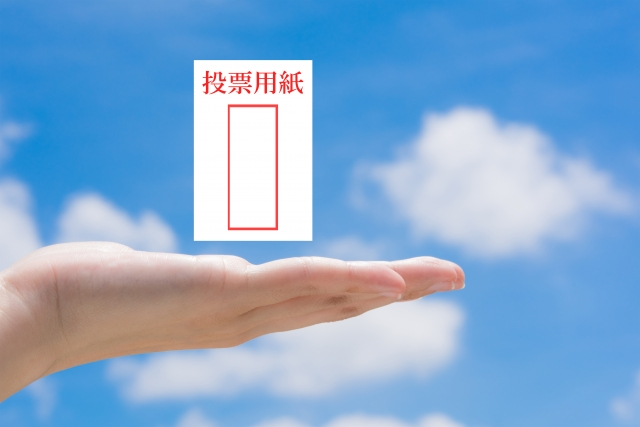
「でも、政治って、自分には関係ないんじゃない?」
そんなふうに感じる人もいるかもしれません。
けれど、政治が決めていることは、じつは私たちの日常にたくさん関わっています。
たとえば
- 学校の授業の内容やテストの制度
- 通学路の安全や道路の整備
- 給食の内容や費用のサポート
- 家族の病院代やお金の制度(税金や給付金など)
こういったことすべてが、法律や予算で決まっているんです。
そして、その法律や予算を決めるのが、衆議院と参議院の仕事です。
つまり、「政治」は遠い世界の話ではなくて、私たちのくらしそのものなんです。
そして将来、20歳以上になって投票できるようになったときに、
「なんでこうなってるんだろう?」
「どうすれば変えられるかな?」
と、自分の考えを持つことがとても大切になります。
衆議院と参議院。
それぞれにちがう役割と力があり、バランスを取りながら国の方向を決めています。
私たちの毎日がその上に成り立っている
そう考えると、「政治を知ること」は、じつは「自分を知ること」に近いのかもしれません。