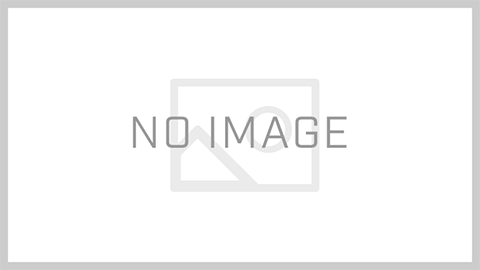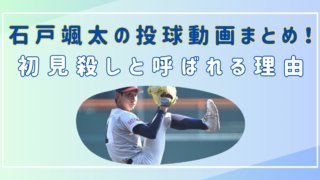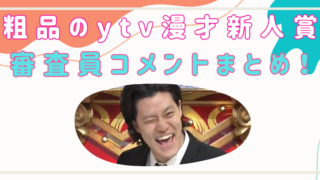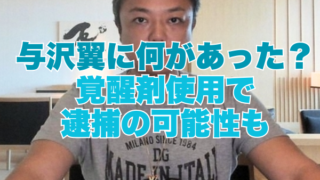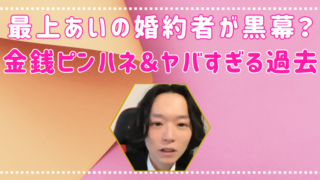日本のお米は高いのになぜ海外では安いのか?理由と裏側を徹底解説!
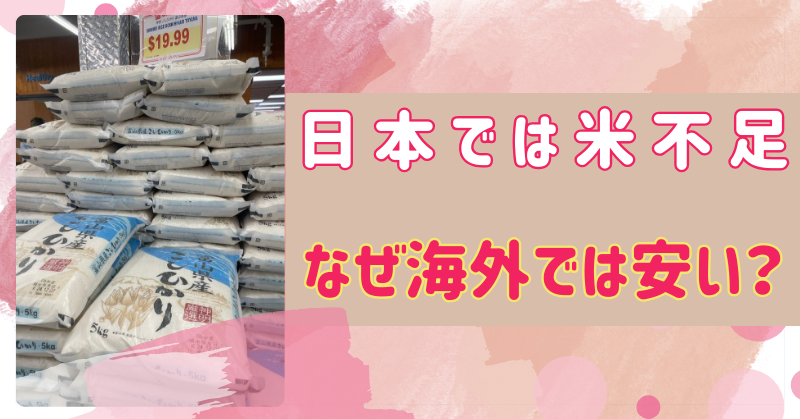
「日本のお米って、なんでこんなに高いの?」
スーパーで値札を見てそう感じたこと、ありませんか?
一方で、海外では“日本米”が驚くほど安く売られているという話も…。
私今こらえてます
アメリカでは新米の時期から日本産コシヒカリ5キロ約3千円でたーくさんあります。なぜ日本が米不足?海外より米が高い?外国米を食べる事になる?おかしすぎませんか。私達の国の農家さんやお米を潰さないで下さい 農家を守って下さい
て、もはや神に頼むしかないのか? pic.twitter.com/oWvhHcrVfx— minmi (@minmidesu) March 24, 2025
いったいこの価格差、どこから来ているのでしょうか?
この記事では、お米が高くなる背景や海外での流通の仕組み、農家さんのリアルな声、そして今の制度が抱える矛盾まで、“モヤモヤの正体”を徹底的に解説します!
読み終える頃には、きっとお米に対する見方が少し変わっているはず。
日常のごはんに隠れた「知られざるストーリー」をのぞいてみませんか?
お米が国内で高くなってる理由
最近、お米の値段がグッと上がったと感じる方も多いのではないでしょうか。
スーパーで5kgで4,500円なんて値札を見ると、「えっ、こんなに高かったっけ!?」と驚きますよね。
でも、実はこの“高騰”、ちゃんと理由があるんです。
その背景には、日本独自の農業政策や、生産コストの上昇が深く関わっています。
まず注目したいのが「減反(げんたん)政策」。
これは簡単に言うと、「お米を作りすぎないでね」と国が農家にお願いしてきた制度です。
お米が余ってしまうと値段が崩れるので、それを防ぐために始まったんですね。
ですが、この政策が長年続いてきたことで、今では田んぼの多くが使われずじまい。
農林水産省の2023年度のデータでは、なんと約35万ヘクタール分の田んぼが使われていません。
当然ですが、生産量が減れば、お米の価格も上がってしまいます。
加えて、近年は肥料や資材の価格も急騰。
例えば、日本経済新聞によると2023年と比べて肥料の価格は約1.5倍、1トンあたり50万円を超えることもあるそうです。
その理由は円安。
海外からの輸入品が軒並み高くなっているんですね。
もちろん、その負担は農家だけで抱えきれず、最終的には私たち消費者の“お会計”に反映されることになります。
そして忘れてはいけないのがJA(農業協同組合)を通すコスト。
農家が直接販売するわけではなく、JAが集めて流通させるため、ここでも手数料がかかってしまうのです。
その額は1kgあたり50円ほどとも言われています。
「最近、お米売り場の棚がスカスカで、しかも高い…」
という声をよく聞きますが、このような複雑な背景が絡んでいるんです。
もちろん「農家さんが大変なら、仕方ないかな」と思う気持ちもありますよね。
でもやっぱり、手に取りやすい価格で、日常的に買える環境であってほしいものです。
国内で買えない米が海外で安い謎
「日本では高くて買えないのに、なんで海外では安いの?」
そう感じたこと、ありませんか?
実際、アメリカのスーパーで“日本米”が5kg3,000円前後で売られているケースも。
一見すると、「なんでそっちのほうが安いの!?」とモヤモヤしますよね。
でも、これにはいくつかのカラクリがあるんです。
まず、海外に輸出されているお米の種類。
2023年の農林水産省のデータによると、日本から輸出されたお米は約2万5,000トン。
でも、実はそのほとんどが業務用だったり、精米から時間が経った“古米”だったりするんです。
つまり、国内のスーパーで売られている新鮮なコシヒカリやあきたこまちとは、ちょっと違うんですね。
例えば、アメリカの人気日系スーパー「ニジヤ」では、ジャポニカ米が1kgあたり300円ほどでセールされていることもあります。
でも、よく見ると精米から3ヶ月以上経過したもので、いわゆる“型落ち品”。
本来の価格は、もっと高めなんです。
さらに、海外では“米の価格競争”がかなり激しい!
カリフォルニア米は1kg200円以下、タイ米にいたってはそれ以下という安さ。
そんな中、日本のお米を売るためには、価格を下げざるを得ないんですね。
実際、2024年には香港向けに出荷された余剰米が、1kgたったの約20円で取引されたという例もSNSで書き込まれてました。
「えっ、それって卸値どころか、ほぼタダじゃん…」
という驚きの価格です。
もちろん、政府としても「輸出倍増計画」として補助金を出し、海外展開を後押ししています。
ですが、輸出量は日本国内の消費量(年間約900万トン)のほんの1%未満。
まだまだ“本格的な輸出産業”とは言えません。
中には「輸出すれば戻し税で得だから」といった声もありますが、「日本人がお米を食べなくなったから、海外に販路を求めた」という冷静な見方も。
とはいえ、国内でお米が品薄になっているのに、海外で“ジャポニカ米特売セール!”なんて見かけると、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。
農家の本音はどう?
「お米が高いのは農家のせい?」
そんな声を聞くこともありますが、実際に現場で汗を流す農家さんの気持ちは、ちょっと違うようです。
まず、忘れてはいけないのが“コストの重さ”。
肥料や農薬の値上がりはもちろん、機械のメンテナンス費用、燃料代、人手不足による外注費など…
年々、出ていくお金は増える一方です。
「お米って売ってもあまり儲からないんですよ」
そんな声を、農家のインタビューやSNSでもよく見かけます。
実際、1俵(60kg)あたり1万円前後で買い取られても、
そこから資材代や手間を引いたら、手元に残るのはごくわずか。
中には「コンビニでバイトした方が稼げる」なんて言う人もいるくらいです。
さらに、
「せっかく作ったのに売れない」
「収穫しても倉庫に眠るだけ」という声もちらほら。
特に減反や流通ルートの問題で、出荷のチャンスが限られている現状では、「やる気を出しても報われない」と感じている農家さんも少なくありません。
「海外で日本米が安く売られてるって聞いたけど、こっちはギリギリでやってるのに…」
というような、やるせなさもあるでしょう。
また、高齢化も深刻です。
後継者が見つからず、「この世代で終わりかもしれない」と悩む家庭も。
未来の農業を担う若者が育ちにくい環境なのも、根深い課題のひとつです。
- 「美味しいお米を作りたい」
- 「日本の食卓を守りたい」
そんな想いを持っている人がたくさんいるのに、その努力が報われにくい構造に、モヤモヤが募っているんです。
だからこそ、私たちも「高い=儲かってる」ではなく、「その背景には何があるのか?」と少し立ち止まって考えてみたいですよね。
誰がこんな状況を招いたのか?
ここまで読んで、「じゃあ結局、誰のせいでこんなことになってるの?」と感じた方も多いかもしれません。
お米が高くて買えない。
なのに海外では安売りされている――。
この“ねじれた現実”を作り出してしまった背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
まず、長年続いてきた農業政策の影響は大きいです。
たとえば、1970年代から本格的に導入された減反政策。
当時はお米が余っていたため、作りすぎを防ぐ必要がありました。
でも、その流れが何十年も続いてしまった結果、“作らないことに慣れてしまった”土壌ができてしまったんです。
しかも補助金でバランスを取る仕組みだったため、根本的な改善にはつながらず。
加えて、国内の食生活の変化も見逃せません。
パンやパスタなどの“主食の多様化”が進み、お米の消費量は右肩下がり。
「売れないから作れない」
「作れないから値段が上がる」
という悪循環にハマってしまったんですね。
そしてもうひとつ大きいのが、流通と仕組みの問題。
JAや市場を通すごとにコストが増え、生産者も消費者も「割に合わない」と感じてしまう。
一方、政府は輸出を促進しつつも、国内の食卓とのバランスには手が回っていないのが現実です。
責任の所在を一概に「誰か一人」に求めるのは難しいですが、言えるのは「時代の変化に制度が追いついていない」ということ。
農家も消費者も、どちらも困っている今の状況こそ、見直しのタイミングなのかもしれません。