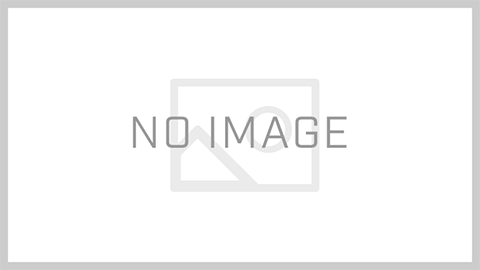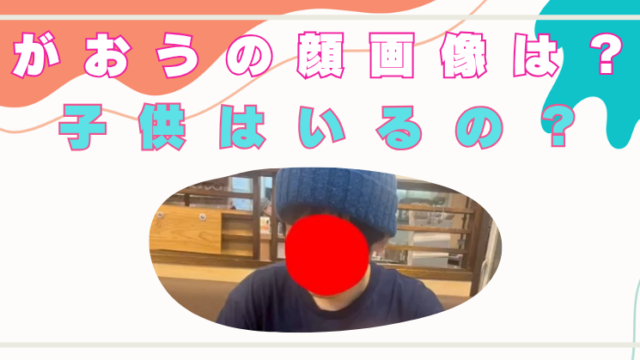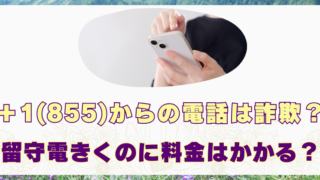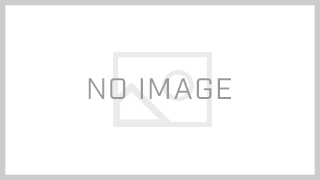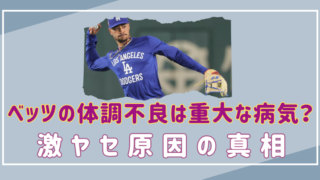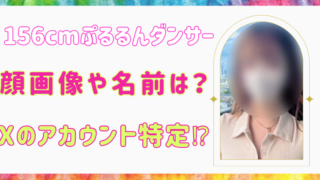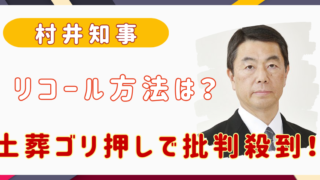ヒカマーって何のこと?ヒカキンファンとの違いが闇深い
SNSでじわじわと見かけるようになった「ヒカマー」という不思議な言葉。
一見すると、YouTube界のトップ・ヒカキンさんの熱烈なファンを指す言葉に思えますが、実はそう単純ではありません。
このスラングには、応援という名の過剰な執着、そして“いじり”や“皮肉”が複雑に混ざり合った、ネット特有の文化的背景があります。
中には「ヒカマー=可哀想」「信者がキモい」といった誤解や冷笑まで飛び交い、ヒカキン本人のイメージにまで影を落とすケースも。
では、普通のヒカキンファンとヒカマーの違いとは何なのか?
この記事では、「ヒカマー」という言葉の意味と成り立ち、ファンとの決定的な違い、さらにはネット文化における“象徴的存在”としての位置づけまで、丁寧に解説していきます。
ヒカマーとは?
最初に「ヒカマー」という言葉を聞いたとき、私は単純に「ヒカキンのファンをそう呼ぶのかな」と思いました。
でも、少し調べてみるとそれは全然違っていたんです。
実際にはもっとクセがあって、ちょっと怖さすら感じるネット用語でした。
私のようにYouTubeを日常的に見ている人なら、ヒカキンさんの名前を知らない人はほとんどいないでしょう。
親しみやすいキャラクターと、家族でも安心して見られるコンテンツで長年トップを走り続けてきた存在です。
ただ、その人気があまりに大きくなりすぎたせいか、ファンの中には極端な行動をする人たちも出てきました。
そして、そういった“過剰にヒカキンにのめり込んだ層”や、“ヒカキンという存在そのものをネタにする人たち”を、ある種の皮肉を込めて「ヒカマー」と呼ぶようになったのです。
つまり「ヒカマー」は、ただのファンとは違います。
応援しているようでいて、時には揶揄の対象にもされる。
言い換えれば、ヒカキンを信仰にも近い形で“祭り上げる”存在、またはそれを面白がって“いじる”存在。
その両極を含んだ、ネット特有の曖昧で皮肉めいた言葉なんです。
たとえばX(旧Twitter)や掲示板では、ヒカキンのちょっとした行動に対して、異様なまでに反応するアカウントを見かけます。
「さすが神」
「ヒカ様、今日も我々に笑顔を…」
など、明らかにネタっぽい言葉で持ち上げているケースも多く、そうしたコメントがヒカマーの代表例とされることも。
一方で、「ヒカマー=頭おかしい信者」といった、悪意を込めたレッテルとして使われる場面もあります。
それを面白がって広める人もいれば、真面目に怒っている人もいる。
つまり、使う側によって意味が変わる、非常に文脈依存なスラングだと言えるでしょう。
興味深いのは、この言葉がヒカキン本人から発信されたものではなく、あくまで外部の人間から“勝手に”生み出されたという点です。
ファンが自称する呼び名ではない。
だからこそ、余計に皮肉や揶揄の意味が強く出てしまう。
「マー」という語尾は、他のインフルエンサーやキャラクターにも応用されるネット文化的な形式です。
たとえばある時期、「○○マー」と名付けられた派閥やファンネームが急増しました。
これはファンダムの過激化や、ネット内でのネタ構造の発展と関係しています。
「○○マー」と名付ければ、単なる支持者ではなく、“異質な集団”として面白がる余地ができる。
その意味で、ヒカマーはヒカキンのファンというより、「ヒカキンをネタにした集合的現象」に近い存在なのです。
あるとき知り合いの小学生が「僕ヒカマーだから」と冗談交じりに言っているのを聞いて、ちょっと複雑な気持ちになりました。
彼は意味を知らず、ただヒカキンが好きという気持ちでそう言ったのだと思います。
けれど、その言葉の裏にあるネットの空気を知っている私からすると、「いや、それは言わない方がいいかも」と止めたくなるような、そんな感覚だったのです。
このように、ヒカマーという言葉には、表面的な意味以上の深みがあります。
単なるファン呼称として片付けられない背景、そしてネット文化が生み出す集団心理や言葉の暴走。
次のセクションでは、ヒカマーと“本来のファン”との違いについて、より具体的に見ていきます。
ヒカキンファンとの決定的な違いとは
ある日、会社の後輩とランチをしていたときのことです。
話題は自然とYouTubeの話に移り、「そういえばヒカマーって知ってます?」と後輩が聞いてきました。
私は「まぁ、知ってるけど……」と返すと、彼女は少しだけ苦笑いを浮かべながら言ったのです。
「なんか、普通のファンと違うんですよね。あれ、ヒカキン本人からしたら迷惑じゃないかなって思って……」
その一言に、私は妙に納得してしまいました。
「ヒカキンファン」と「ヒカマー」。
両者の違いを説明するなら、それは“応援の仕方”と“態度の温度差”に集約されます。
まずヒカキンファンは、動画を見て楽しみ、グッズを買って応援し、SNSでポジティブな言葉を送る、いわば王道の支援スタイルです。
その存在はクリエイターにとっても励みになるでしょう。
一方でヒカマーと呼ばれる人々は、やや異質な側面を持っています。
ヒカマーの特徴をひとことで言えば、「過剰さ」です。
たとえば、
- ヒカキンの食べたものを即日マネして同じ構図で投稿
- どんな出来事にも「ヒカ様ならこう言う」と勝手に妄想を加える
- 他のYouTuberを過度に貶してヒカキンを持ち上げる
といった行動が挙げられます。
もちろん、それらが“愛ゆえ”である可能性も否定はできません。
しかし、行き過ぎた行動や空気の読めない投稿が重なると、周囲から「ちょっと痛い存在」として認識されてしまうのです。
ヒカマーって要するに積極的に加害しに来る淫夢厨みたいなもんやろ
マジで薄気味悪い
知り合いがヒカマーとかやってたら殴ると思う— ぺぺかす (@atlantickSalmon) August 29, 2025
さらに、ヒカマーはヒカキン本人のイメージにまで影響を及ぼす存在でもあります。
たとえば、ネットで「ヒカマーって信者キモいよな」という投稿が拡散された場合、そこにヒカキン本人は無関係なのに、彼自身の評価まで悪くなってしまう。
純粋に応援しているファンからすれば、「一緒にしないで」という気持ちになるのも当然です。
その一方で、ヒカマーはヒカキンを“神格化”するだけではなく、逆に“いじり倒す”スタンスで関わるケースも多いのが特徴です。
例えば、
- 「ヒカキンが言えば税金も払うわ(笑)」
- 「ヒカキン様に見られてると思うと掃除も捗る」
といった投稿は、一見して褒めているようでいて、どこかネタ化・偶像化されている印象を受けます。
このように、ヒカマーという言葉には“盲目的に信仰する存在”と“偶像をネタにする存在”の両極が同居しているのです。
さらにややこしいのは、ヒカマーと名乗っている人たちの中にも、自分がどちら側なのか分かっていないケースがあること。
本気で信仰しているのか、冗談なのか、それすら曖昧なまま言葉だけが一人歩きしている。
こうした“ネット的ノリ”が、ヒカマーという存在をさらに複雑にしています。
以前、ある投稿が話題になりました。
「ヒカマーのせいで、普通のファンまで変な目で見られる」
このコメントには、いいねや共感の声が多数集まっていました。
それはつまり、ヒカマーという言葉が「一部の過激な存在」を超えて、“レッテル”として独り歩きし始めた証でもあります。
私が注目したいのは、この構造が別にヒカキンだけに起きているわけではない、という点です。
人気のある芸能人や配信者、アイドルにも、たいてい同じような“熱狂層”と“ネタ層”が存在します。
そして彼らの一部が、周囲からの揶揄や批判の対象になってしまう。
つまりヒカマーは、現代のファンダム文化が抱える「共感と過熱」の問題を象徴しているとも言えるのです。
ファンとヒカマー。
似て非なるこの2つは、「応援する」ことと「崇拝・ネタ化する」ことの分かれ道を教えてくれます。
言葉だけで括ると同じように見えて、実際には行動や周囲への影響がまったく異なるのです。
次は、「なぜヒカマーは“可哀想”と言われるのか?」という一歩踏み込んだテーマへと進みます。
この呼び名が生んでしまった、ヒカキン本人に対する“無関係な逆風”について掘り下げていきます。
なぜヒカマーは可哀想と言われるのか
「ヒカマーって、なんか可哀想だよね」
ある日、SNSを眺めていたときに、そんなつぶやきを見かけました。
そのとき私は、「いやいや、ちょっと揶揄されてるだけでしょ」と軽く流しかけたのですが、その後に続いた一文にドキッとさせられたんです。
「だって、本人が望んでない呼び方で、勝手にファン扱いされてるんだから」
たしかに、その通りかもしれません。
「ヒカマー」という言葉は、ヒカキン自身が使い始めたわけでもなければ、ファンの間で自然に生まれた愛称でもない。
第三者が“半ば冗談として”“ちょっと小馬鹿にするようなテンションで”作ったネットスラングです。
にもかかわらず、それがファン全体の呼称のように使われ始め、純粋に応援している人まで巻き込まれてしまっている。
その構造は、たしかに「可哀想」と言われるに値するかもしれません。
もっと問題なのは、ヒカマーという言葉が、ヒカキン本人にも“逆風”となり得ることです。
SNSの一部では、「ヒカマーうざい」「信者キモい」といった言葉が並び、それに対する“カウンター”としてヒカキンの名前が持ち出されることがあります。
「ヒカマーって言われてるファンが多いってことは、ヒカキンってヤバいの?」という誤解まで生まれることもあるのです。
これって、本人にとってすごく理不尽な話ですよね。
ヒカキンは、炎上系でもなく、過激なことをするタイプでもない。
むしろ真面目で、品のある動画づくりを長年続けてきた数少ないYouTuberです。
Xそれでも「ヒカマーがうるさい」という理由で、彼自身が「なんか変な人たちに好かれてる人」という印象を持たれてしまう。
本人にはどうすることもできない“ネットスラングの罠”とも言えます。
私がある意味で一番怖いと思ったのは、「ヒカマー」という言葉が、ある種の“冷笑文化”に取り込まれているという点です。
ネットでは時として、「応援してる人」よりも「応援をバカにする人」のほうが優位に立つ風潮があります。
本気でファンをやっている人に対して、「必死すぎ」「信者かよ」と冷ややかなコメントを飛ばすことで、逆に自分の立場を守る。
「ヒカマー」は、そうした冷笑的ネット気質にぴったりはまるラベルになってしまっているのです。
さらに問題なのは、そういった“バカにする空気”に、無自覚な人まで乗っかってしまう点です。
たとえば、ある中学生がヒカキンの動画を楽しんでいるというだけで、周囲から「お前ヒカマーかよw」とからかわれる。
笑いながら冗談として言ったつもりでも、言われた側は少なからず傷ついてしまうでしょう。
これが大人の世界でも起きているとしたら、非常に根深い問題です。
言葉は、使う人の意図と、受け取る人の解釈の間にギャップが生まれやすいもの。
「ヒカマー」という言葉は、まさにそのギャップの象徴です。
使っている側は“軽いノリ”でも、受け取る側にとっては“レッテル”や“偏見”となる。
そのことに無自覚なまま、スラングが一人歩きしてしまうのが、いちばん恐ろしいところかもしれません。
そして何より、この騒動に一番巻き込まれてしまっているのは、ヒカキン本人です。
彼はファンを大切にする人として知られています。
炎上にも乗らず、誠実な動画づくりを何年も続けてきた。
そんな彼の活動が、一部のネットスラングによって誤解されるのは、本当に可哀想な話です。
もちろん、ファンダムにはいろんな人がいて、過激な人もいるでしょう。
それでも「応援すること」が悪であるかのように語られる空気が広がるのは、あまりに不健全です。
ヒカマーという言葉が広がることで、「ファン=痛い」「ヒカキン=信者の象徴」といったイメージが出来上がってしまうなら、それは誰にとっても損失でしかありません。