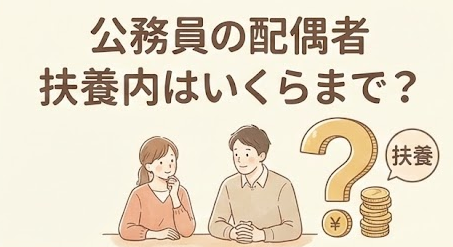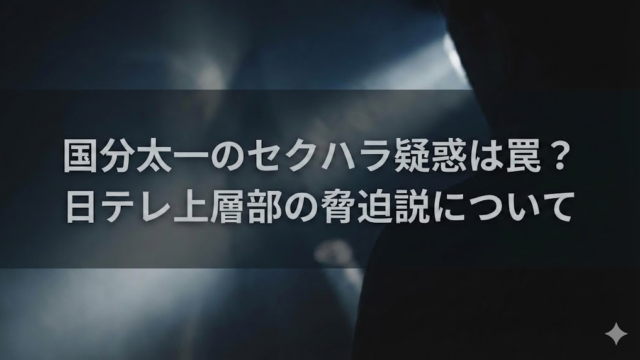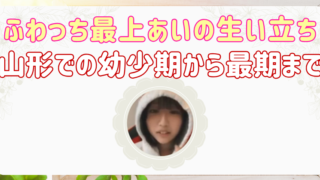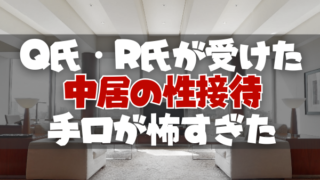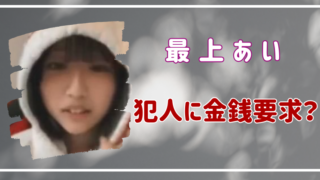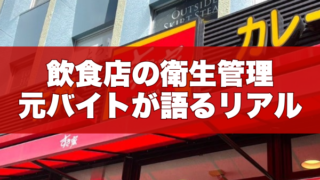海外の地震リスクが高すぎる…!日本との耐震基準の違いを解説

海外旅行や移住先として人気のタイや東南アジア。
リゾート地やグルメ、物価の安さなど魅力がいっぱいですが――
実はあまり知られていない、「地震」に関する重大なギャップがあることをご存じでしょうか?
「日本と同じ感覚で安心していたら危ないかもしれない」
そんな声が少しずつ広がりはじめたのは、大地震によってバンコクで起きた建物倒壊がきっかけでした。
タイとミャンマーの国境で発生したマグニチュード7.7の地震で、バンコクで建設中の超高層ビルが崩壊する様子を示す追加映像。
悲惨すぎる…。 pic.twitter.com/FG0H1AOpYG— CIPHER (@CIPHER1978) March 28, 2025
一方、地震が起きた際に、多くの人がこのビルの下に避難していたという大林組のオフィスビル。
【プレスリリース】
タイ大林がバンコク中心部で大型オフィスビル「O-NES TOWER」を開業しました。現代美術作家 #杉本博司 氏のパブリックアートがタイで初めて実現。杉本氏率いる #新素材研究所 がデザイン監修した前庭もできました。#大林組 #開発▷https://t.co/nN2lFp9zyS pic.twitter.com/2L1j58PLpz
— 大林組【公式】 (@OBAYASHI_JP) March 24, 2022
日本ではあたり前とされている「耐震基準」。
でも、それが世界のスタンダードだとは限らないんです。
地震そのものではなく、“建物の差”が命運を分ける現実。
この先、安全な海外滞在や旅行を考えている方なら、知っておいて損はありません。
「海外の地震リスクが高すぎる」と言われる背景には、実は深い理由があったのです――。
海外の地震リスクが高い理由
地震って、日本だけの話じゃないの?と思っていませんか?
実は最近、そんな常識が覆される出来事が起こりました。
2025年3月28日、ミャンマーで発生したマグニチュード7.7の大地震。
なんと震源から約1,000kmも離れたタイ・バンコクで、建設中の33階建て高層ビルが倒壊したんです。
これ、ちょっと信じられないですよね。
日本でいえば、北海道の地震で東京のビルが崩れるような感覚。
一瞬で崩落したビルの映像は世界中の人たちに衝撃を与えました。
詳しくは以下の記事も読んでみてください。
なぜこんなことが起きたのか?
主な原因は「長周期地震動」。
遠くの大地震が、高層ビルを揺らす“ゆっくり大きな揺れ”のことです。
そしてバンコクは地盤が柔らかく、この揺れを何倍にも増幅してしまうんです。
さらに問題なのは、耐震基準の甘さ。
バンコクは地震が少ない地域とされているため、「まさかこんなに揺れるなんて」という想定外の揺れへの備えがほぼゼロ。
同じようなことは他国でも。
たとえば2023年の**トルコ地震(M7.8)**では、20万棟以上の建物が倒壊。
原因は「違法建築の容認」や「建築基準の未整備」。
結果として、5万6,000人以上が亡くなったという現実があります。
つまり、海外では
地震が少ない=建物が弱い
という落とし穴がたくさんあるということ。
地震が“来るかもしれない”国ではなく、“来ないと思われてる”国こそ、要注意かもしれません。
日本は鉄壁!耐震基準の差がスゴい
地震の多い日本で、私たちは当たり前のように“揺れに強い建物”に守られています。
でもその「当たり前」、実は世界的に見ると、異常レベルにハイスペックなんです。
1981年に導入された「新耐震基準」では、震度6強〜7の地震でも倒壊しないことが義務に。
1995年の阪神淡路大震災(M7.3)では、この新基準のビルが大きく生き残りました。
そして2011年の東日本大震災(M9.0)。
東京の高層ビルが10分以上揺れ続けても倒壊せず、
走行中の新幹線27本はすべて即時停止、死傷者ゼロという驚異の結果に。
これ、海外では「SFかよ…」と言われるほど。
実際、海外の建築関係者が日本のビルや交通システムを見ると、
- 「どうしてこんなに早く止まるの?」
- 「なんでビルが無事なの?」
と驚くことも多いのだそうです。
しかも、建物の設計段階で地盤の強度や揺れの伝わり方をシミュレーションし、地震のエネルギーを吸収する「免震」や「制震」技術も導入。
つまり、建物自体が“揺れと一緒にダンスして耐える”ように作られているんです。
ちょっと何を言っているかわからない人もいると思うので、一応、動画を貼っておきますね。
この右端のが免震構造のビルということですね。
そして何よりすごいのが、国民の防災意識。
避難訓練は日常の一部だし、「この公園が避難場所」って知ってる人、けっこういますよね?
海外では、それすら知られてない国も少なくありません。
こうして見ると、日本の耐震対策って、**世界トップレベルどころか“別次元”**なのかも。
タイ地震で大林組のビルが優秀だった話
実際、現地でも日本の耐震技術が信頼を集める場面がありました。
バンコクで注目されたのは、大林組の現地法人「タイ大林」が手がけたO-NES TOWER(オーネスタワー)。
BTSナナ駅直結の複合ビルで、2022年に完成した29階建ての最新鋭オフィスビルです。

ミャンマー地震の際、周囲の高層ビルが揺れや損傷を受ける中、O-NES TOWERはほぼ無傷。
SNSでも
- 「びくともしなかった」
- 「安心感が違う」
- 「さすが日本が誇る大林組」
と高評価が相次ぎました。
ミャンマーの地震で、日本の大林組が建てたビルの耐震性についてのツイ見たけど、これから日本の耐震技術が世界で注目されるかな?やっぱり日本は観光立国よりも技術立国した方がいいと思うの。
— 真希(子) (@shika223508) March 30, 2025
その秘密は、日本で培われた耐震技術にあります。
- 工場で精密に作られたプレキャストコンクリートパネル
- 揺れを吸収する可動式ジョイント
- そして強度と耐火性を兼ね備えたCFT柱(コンクリート充填鋼管)
これらは、1981年以降の日本の新耐震基準をベースに導入された技術。
まさに“地震に耐えるために設計されたビル”の力を、海外で証明した事例といえますね。
Construction workers at Cloud 11 Sukhumvit 101 evacuated following the tremors in Bangkok, triggered by a 7.7 magnitude #earthquake in #Myanmar pic.twitter.com/OCc9YTDGrb
— INO@Thailand (@INO_Thailand) March 28, 2025
上は大林組が現在建設中のビル(地震後)。
建物の外より中に居たほうが安全であることが伺えます。
いま東南アジアは危ない?余震は大丈夫?
東南アジアといえば、旅行先としても人気ですよね。
タイ、ミャンマー、インドネシア、フィリピン…。
でもいま、「行って大丈夫?」と不安になる人も増えています。
まず、2025年3月のミャンマー地震以降、専門家はM6クラスの余震が起きる可能性があると警告。
地震は一度起きると、数週間〜数ヶ月、揺れが続くことも珍しくありません。
特にタイ・バンコクは、地盤が柔らかく揺れが増幅しやすい土地。
高層ビルが多く、耐震基準も緩めなため、ちょっとした揺れでも被害が出る可能性があります。
実際、今回倒壊した33階建てのビルも、建設中で補強が不十分な状態でした。
SNSでは「中国企業の手抜きだった?」といった声も出ていますが、構造的な選択ミスや、耐震設計の甘さが根本にあるとみられています。
さらに驚きなのは、完成済みの高級コンドミニアム「Hampton Residence Thonglor」でも、2棟をつなぐスカイブリッジが地震で落下したという報告。
建物自体は無事でも、「橋が落ちる」って、正直怖すぎますよね。
ミャンマー地震の揺れで、ビル間の歩道が避けてしまった模様😨
トンローにあるパークオリジンの建物間の歩道が裂けたようだ。怖いねぇ。
— 🅿️MAN (@avenanthramide) March 28, 2025
こうした現状を見て、タイだけでなく東南アジア全体が「地震に甘い」と感じる人も。
インドネシアやフィリピンのように、地震が多いのに耐震意識が追いついていない国も多いのです。
たとえば、同じ震度4の揺れでも、日本の建物なら無傷でも、海外では倒壊するリスクがあるんです。
これは、建物の耐震設計そのものが違うから。
日本では震度6強〜7でも耐える設計が標準ですが、東南アジアなどでは震度5程度も想定外だったりしますからね。
結果、揺れの大きさは同じでも『被害の深刻度がまったく違う』ということになります。
とはいえ、すべての場所が危険というわけではありません。
旅を楽しむなら、宿泊先の築年数や構造、安全評価を事前にチェックしておくと安心。
「東南アジアだから油断しちゃダメ」
それが今回の地震が教えてくれた最大のメッセージかもしれません。