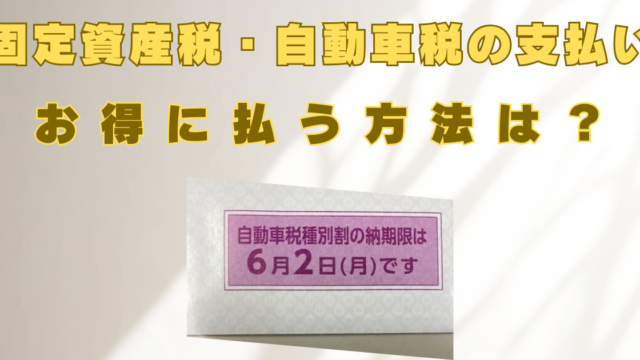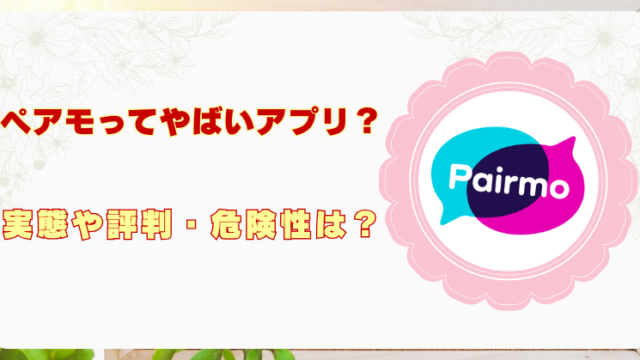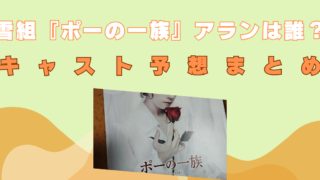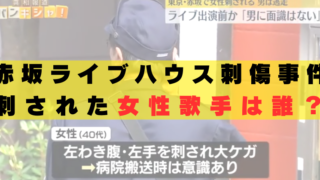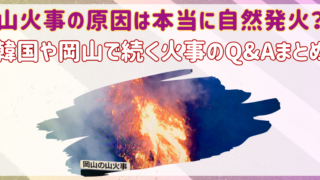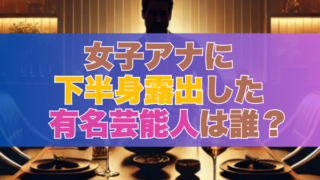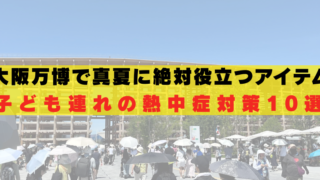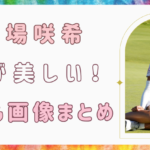駿台ベネッセと全統プレどっちを信じる?共通テスト本番の難易度予想
模試の点数が下がっただけで「終わったかも」と感じている人も多いですよね。
とくに駿台ベネッセ模試と全統プレ模試で大きな差が出たとき、「どっちの結果を信じればいいの?」と迷うのは自然なこと。
でもその違い、実は点数よりも“ある視点”で見たほうが本番に活きてくるんです。
さらに、2026年の共通テスト本番の難易度はどうなるのか?
模試と本番、その“温度差”に振り回されないために、今、知っておくべきことがあります。
そんなあなたの「今どこに立っているのか」を整理するヒント、この記事でじっくり紐解いていきましょう。
駿台ベネッセと全統プレの違いとは
11月に行われた「駿台・ベネッセ共通テスト模試(通称:駿ベネ)」と、「全統プレ共通テスト(河合塾主催)」。
この2つ同じように見えて、じつは性格がまるでちがうんです。
まず、受けている人の層が違います。
駿ベネは、全国の高校生が団体で受けることが多く、現役生メインの28万人規模。
一方、全統プレは現役+浪人+東大・京大志望が多めの42万人規模で、いわば“受験ガチ勢”がゴロゴロ。
この母集団の違いだけでも、偏差値が5〜8くらい変わることもあります。
そして、出題のクセにも違いが。
駿ベネは「標準〜やや難」とされていて、本番の形式にそっくりな作り。
でも、後半に応用問題が出てくることが多く、「おや?これはなかなか」と思わせる良い意味でクセのある問題がちらほら。
それに対して全統プレは、「本番同等〜やややさしめ」に仕上げているのが特徴。
ただし、時間配分をミスると一気に崩れるような構成になっていて、油断は禁物です。
とくに2025年11月16日の全統プレでは、物理で波動の実験問題が出され、「計算量が本番並みで時間切れ続出」と話題に。
化学では有機のグラフ読み取りがやや難しく、Xでは「平均点が理系全体で前回比マイナス10点」との声も見られました。
「駿ベネでは650点台だったけど、全統プレでは580点…理科が一気に難化した印象」
こんなつぶやきも、共感を集めていました。
たとえるなら、駿ベネ=健康診断(いまの実力チェック)、全統プレ=模擬手術(本番環境でのトライアル)。
それぞれ役割がちがうから、点数のズレが出るのは当たり前なんです。
なので、「私、504点しか取れなかった…」と落ち込む必要はありません。
実際は「その点数=その模試での力」でしかなく、本番で+50点のポテンシャルがあるという見方もできるんです。
それでも気になるのが「じゃあどっちを信じればいいの?」という話。
次のパートでは、その答えを一緒に探っていきましょう。
どっちを信じるべき?判断ポイントを解説
模試の点数が大きく下がると、つい焦ってしまいますよね。
「このままじゃ志望校ムリかも…」なんて、夜な夜な考えこんでしまう人も多いんじゃないでしょうか。
でも、ちょっとだけ目線を変えてみてほしいんです。
本当に見ておくべきは、点数の上下じゃなくて“何を間違えたか”“何が解けたか”の中身なんですよ。
これって、意外とみんなスルーしがち。
たとえば、理系で駿ベネの数学IAが70点、全統プレでは50点だったとします。
パッと見ると「下がってる、ヤバい」となりますが、実は駿ベネは典型パターンの誘導問題が中心。
一方で、全統プレでは計算量が多くて時間配分を間違えやすい構造問題が出やすい傾向があるんです。
この場合、単に「力不足」じゃなくて、「時間管理と捨て問の判断」に課題があるってこと。
つまり、同じ数学でも、模試ごとに試される“能力”が違うんです。
Xでもよく見かけますが、「ケアレスミスで10点損した」「選択肢を読み違えた」なんて失点、実力とは関係ないことも多い。
だからこそ、「今回のミスは何が原因?」と自分で“採点会議”を開くクセをつけておくと、本番に強くなります。
それに、全統プレにはちょっと便利な機能があるのをご存じでしょうか?
それが「本番換算得点」。
これは、模試の難易度を共通テストの平均点にあわせて補正した予測スコアのようなもの。
たとえば、2025年の理系では全統プレの得点が本番より5〜10%低く出る設計だったと河合塾が公表しています。
つまり、「全統プレで504点だった」という人も、実質550〜600点のポテンシャルがある可能性があるんです。
この数字を知るだけで、「まだ戦える」って思えますよね。
さらに、模試直後のXや知恵袋では、理系生たちのこんな声が増えていました。
「物理の波動実験で時間足りず…」
「化学の有機グラフ、ぜんぶ間違えた…」
ここからも分かる通り、模試は“落とし穴の発見器”みたいなもの。
あなたがハマったそのミス、まさに「本番でも起こり得るポイント」なんです。
逆に言えば、いま気づけたことがラッキー。
そこをひとつずつ潰していけば、点数は自然と伸びていきます。
点数が高かった模試を信じたい気持ち、分かります。
でも、「どっちを信じるべきか?」の本当の答えは、点数じゃなく、“どこを伸ばすか”を教えてくれた模試です。
模試はゴールじゃなくて、地図なんです。
次は、いちばん気になる「本番の難易度はどうなるのか?」について見ていきましょう。
これまでの模試をどう活かすか。
そのヒントが見えてくるはずです。
共通テスト本番の難易度はどうなる?
年が明けると、いよいよ共通テスト本番。
「模試はボロボロだったけど、本番ってもっと難しいの?」
「いや、意外と優しめで助かったりして?」
こんな気持ちが交錯するのも、今の時期ならではです。
さて、実際のところ、2026年の共通テストは“やや難化”する可能性が高いといわれています。
その理由は、新課程になって2年目。
文部科学省が本格的に「思考力・読解力・情報活用力」を見ようとしているからです。
東進や河合塾の最新予想(2025年11月時点)でも、「情報Iと現代文の問3が、差のつきやすいポイントになる」と分析されています。
理系にとって重要なのは、やはり数学と理科。
2025年の共通テストでは、
- 数学IA:57点(前年比+6点)
- 物理:57点(前年比−6点)
- 化学:48点(前年比−7点)
こんな感じで、理系科目はじわっと難化していたのがわかります。
そして、今回の全統プレ(2025年11月16日実施)でも、それを意識した出題が目立ちました。
たとえば物理。
波動の実験問題が出て、「計算が多くて時間切れになった」という声がXで急増。
化学では有機分野のグラフ読み取りで「20点近く落とした」という投稿もチラホラ。
河合塾の速報でも「理系の平均点が前回より10点近く低下」との報告がありました。
これらを見れば、全統プレは本番の傾向とかなり近いことがわかります。
一方で、情報I。
去年(2025年)は平均69点と高得点の科目でしたが、予備校の予想では2026年は難化方向。
プログラミングの基礎や論理的思考が、きちんと問われそうです。
でも、これって逆にチャンスかもしれません。
「今から2か月でやれる範囲」が、そこにはまだあるからです。
何をやればいいのか。
答えはシンプル。
模試で出た“差がついた問題”を中心に、つまずいた理由をあぶり出すことです。
それだけで、あなたの“本番の武器”が増えていきます。
実力は、積み重ねた「気づき」の数で決まるんです。
今回のテーマ
「駿台ベネッセと全統プレどっちを信じる?共通テスト本番の難易度予想」
この問いに対して、はっきり言えることはこうです。
模試の点数より、「そこから何を学んだか」。
そして本番は、「やや難化予想」だけど、対策を重ねた人には“想定内”のテストになります。
あと2か月、あせらず、着実に。
まだまだ、逆転できるタイミングです。