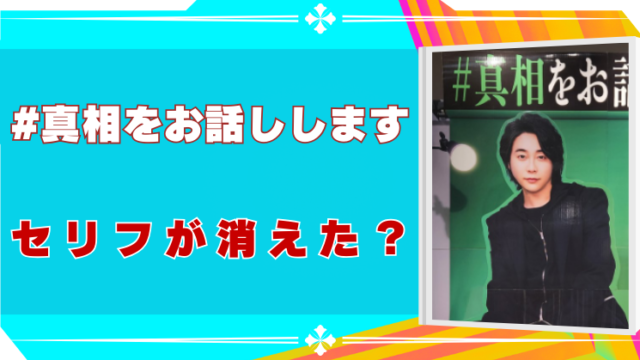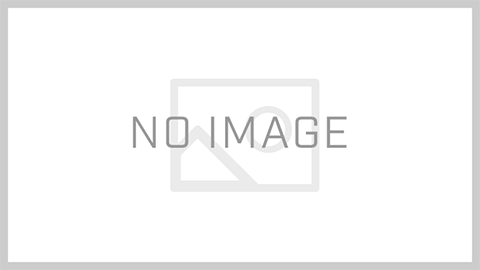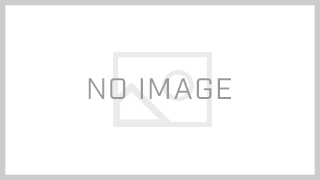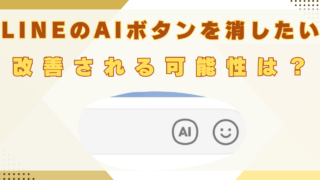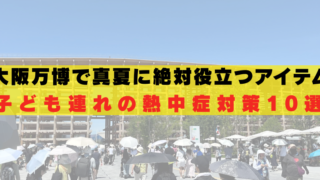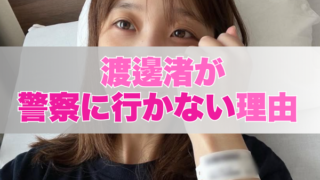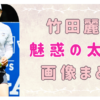リベンジ退職が増える理由
最近よく聞くようになった「リベンジ退職」という言葉。
でもこれ、ただの流行語ではありません。
じつは、今の働き方の根本的な変化を映し出している言葉なんです。
まず、「リベンジ退職」とは何か?
これは、退職する際に、不満や問題点を明確に表明する行為のこと。
「静かに辞めて終わり」ではなく、「自分がどれだけ理不尽を受けてきたか」「この職場の何が問題だったのか」などを、最後にしっかり伝えて去る――
そんな意思表示です。
もちろん、やり方には差があります。
中には極端な例もあります。
たとえば、ある社員が独自に開発した資材管理システムを、退職時にすべて削除して去ったという話。
その結果、社内は大混乱し、真相を知った上層部が激怒。成果を横取りしていた上司は左遷されました。
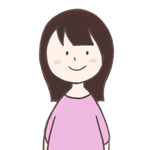
ただし、これはかなり稀なケース。
多くの場合は、退職面談で本音をぶつけたり、社内チャットやSNSで「これまでの問題点」を残したりと、穏やかだけど意味のある“去り方”が選ばれています。
では、なぜ今この「リベンジ退職」が増えているのでしょうか?
ひとことで言えば、「我慢しすぎない」価値観が広がってきたから。
以前は、「嫌でも我慢して続けるのが社会人」とされてきました。
でも今は、「意味のない我慢なら、続ける必要はない」と考える人が増えています。
たとえば、年間営業成績でトップだったのに評価されなかった人。
あるいは、自分の努力が無視され、成果を横取りされた人。
そんな話が、X(旧Twitter)でも次々と共有され、「それ、うちの会社でもあった…」という共感の輪が広がっているのです。
背景には、ワークライフバランスの価値観の変化があります。
「仕事だけの人生でいいのか?」
「理不尽を飲み込んでまで、ここにいる意味ある?」
そんな問いが、あらゆる世代の中で芽生えています。
だからこそ、「辞める=逃げ」ではない。
むしろ、「辞める=正当な意思表示」という風潮が出てきた。
そしてその“辞め方”に、自分の矜持や信念を込める人が増えているんです。
リベンジ退職。
それは、誰かを傷つけるためじゃない。
「これ以上、自分を犠牲にしない」ための選択なんです。
黙って辞めない若者の本音
「引き継ぎはするけど、自分が作った改善案は全部削除してから辞めたって話、見たことある?」
X(旧Twitter)では、そんな投稿が話題になっていました。
極端に思えるかもしれませんが、そこには強い本音が込められているんです。
いま、退職の「去り方」が変わりつつあります。
ただ黙って去るのではなく、自分の意志を残すような辞め方。
一言で言えば、「これは自分の問題じゃない」と伝えて去る選択です。
なぜ、そんな辞め方をする人が増えているのでしょうか?
その理由はシンプル。
がんばっても報われない職場で、自分の尊厳を守る手段だから。
たとえば、営業で圧倒的な成績を残していたのに、上司や人事から正当に評価されなかったケース。
それどころか、負担ばかりが増え、意思確認のない仕事を一方的に押しつけられる。
こうした話、決して珍しくありません。
もちろん企業側にも事情があるとはいえ、現場で働く人のモチベーションが保てない状況は、想像以上に深刻です。
ある人は言いました。
「評価される努力より、無難に従う方が生きやすい会社だった」
それって、悲しすぎませんか?
そしてもう一つ大きな理由が、「何を言っても変わらない」経験の積み重ねです。
日頃から意見を言ってもスルーされたり、逆に浮いた存在にされたり。
だったら最後に“態度で示す”しかない、そう考える人も出てくるのは自然です。
でも、勘違いしないでください。
「会社を困らせたい」からじゃないんです。
「自分の存在が軽く見られたまま終わるのは嫌だ」という、切実な想い。
だからこそ、黙って辞めるのではなく、何かしらのメッセージを残していく。
たとえるなら、何度もチーム内で改善提案していたのに誰にも聞かれず、
最後に「これが私のやってきたことです」と全部まとめて机に置いて去るようなもの。
派手な行動ではないかもしれません。
でも、それは「自分の仕事に誇りを持っていた人」だからこその行動なんです。
これまで「辞めるなら黙って立つ鳥跡を濁さず」が美徳とされてきました。
でも今は、「跡に残さなければ伝わらないこともある」と考える人が増えています。
黙って辞めない――
それは、会社や誰かへの攻撃ではなく、「自分を大事にするための最後の表現」なのかもしれません。
ただ、ネット上にはこんな声もあります。
リベンジ退職は論外だけど、辞める際に
・お前が辞めたら業務が回らなくなったから損害賠償を請求する
・辞めたあとも連絡交換して無償で引き継ぎしろ
・辞めるやつに有給は使わせないって会社も普通にあることを知っておいたほうがいいよ https://t.co/YznJJ5Y7Z1
— ふくえもん / fukuemon (@fukuemon3) September 9, 2025
リベンジ退職が共感される時代背景
「また辞めたってさ」
「最近の人は、我慢がきかないよね」
なんて声を、職場で聞いたことありませんか?
でも今、そうした“辞め方”に対する空気がガラッと変わってきています。
今話題の「リベンジ退職」。
この辞め方が共感されるようになった背景には、いくつかの大きな変化があります。
まずひとつは、価値観の変化。
かつては「とにかく我慢」「長く勤めてなんぼ」という考え方が主流でした。
でも今は、「意味のない我慢はしない」「自分のキャリアは自分で守る」と考える人が増えています。
さらに、働き方の多様化も影響しています。
副業や転職が一般的になり、「この職場にしがみつかなくてもいい」という選択肢がある。
だからこそ、「納得できないなら去る」という決断も、自然なものになってきたのです。
そしてもうひとつ。
声をあげてもいい、という社会の空気。
SNSなどを通じて、他人の体験や価値観を知る機会が増えたことで、
「自分だけじゃなかったんだ」
と気づく人も多くなっています。
具体的なエピソードも紹介します。
ある女性社員は、3年間かけて社内業務の改善案を練っていました。
しかし、提案するたびに「現状で問題ないから」と門前払い。
結局、退職を決意した彼女は、最終日にその改善案を全社員に公開し、静かに去りました。
その数ヶ月後、会社はその案を採用。
でも、誰も彼女の名前を出さなかったそうです。
それって、やるせなさすぎませんか?
こうした体験に、SNSでは「わかる」「うちの職場でも似たようなことがあった」といった声が殺到。
「それでも黙って去るなんて無理だよ」という共感が、広がっているのです。
重要なのは、これは一部の若者だけの話ではないということ。
世代を超えて、多くの人が「黙って辞めない」選択をとり始めている。
そこには、“波風を立てたい”のではなく、“自分の人生を丁寧に扱いたい”という想いがあるのです。
最後に、もう一度振り返ってみてください。
「リベンジ退職に共感が集まる理由」
それは、私たち一人ひとりが、働く中で大切にしてきた信念や苦労を、黙って飲み込むだけで終わらせたくないと願っているからではないでしょうか。
だからこそ、今この言葉が支持されているのです。
黙って辞めない人たちの本音に、共感が集まっている。
それはきっと、あなたの中にも、同じ想いがあるから。