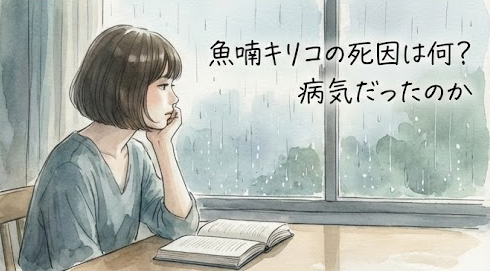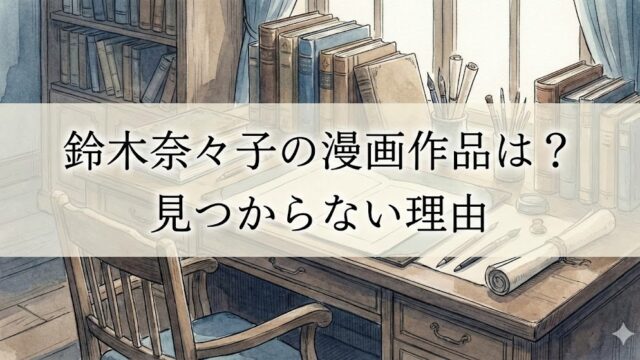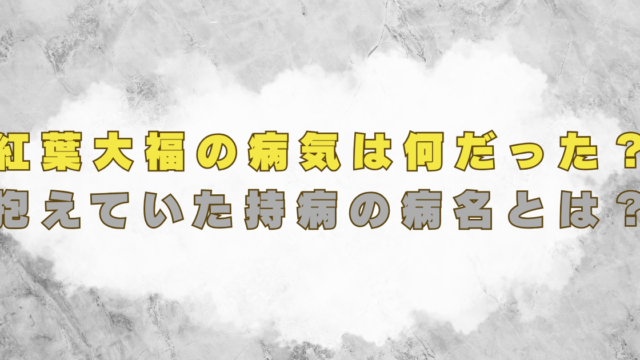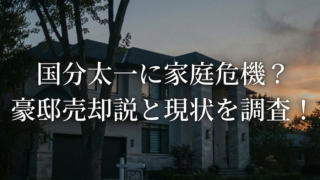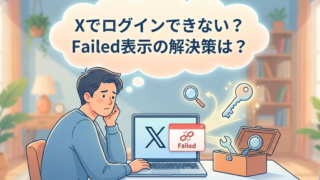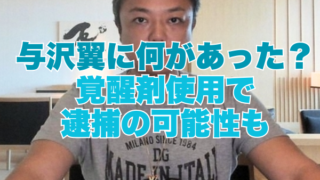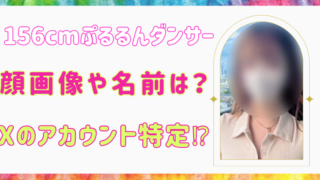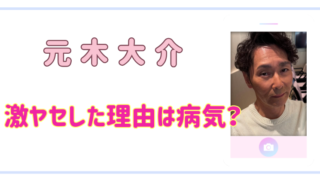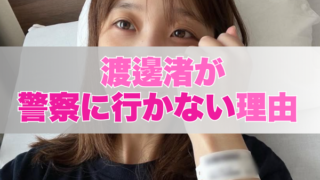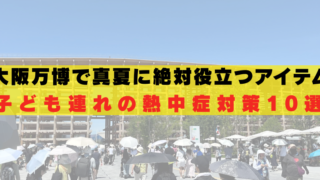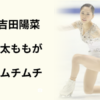細田守はなぜ奥寺佐渡子と組まない?脚本酷評と再タッグの声続出
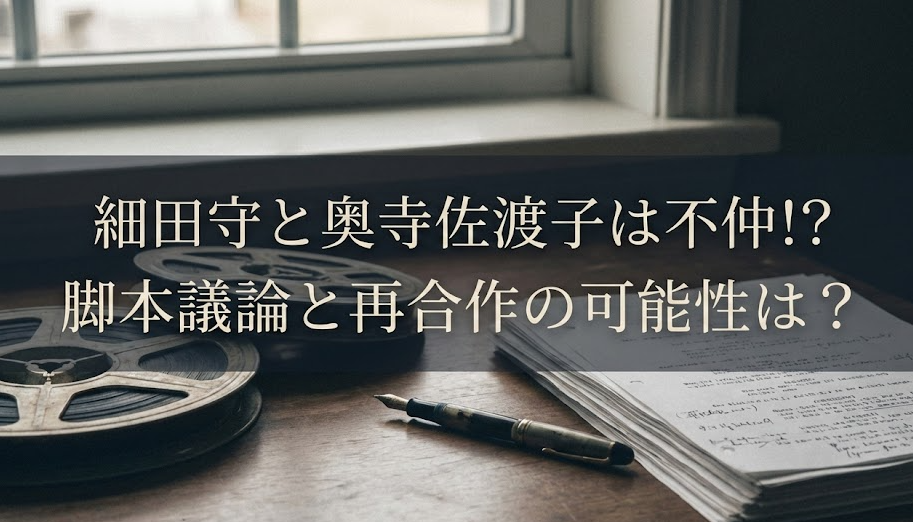
細田守(ほそだまもる)監督の新作が公開されるたびに、X(旧Twitter)やレビューサイトでは「脚本が惜しい」「また奥寺さんと組んでほしい」といった声が後を絶ちません。
とくに2025年11月公開の最新作『果てしなきスカーレット』では、ビジュアルの完成度は高評価なものの、脚本への批判が殺到。
SNS上では「#奥寺佐渡子」がトレンド入りし、かつて名コンビと評された二人の“復活待望論”が一気に広がりました。
この記事では「なぜ奥寺さんと再び組まないのか?」という疑問に焦点を当て、脚本批判の背景や再タッグを望むファンの声、そして細田監督が単独脚本にこだわる理由まで、徹底的に掘り下げていきます。
目次
『果てしなきスカーレット』で細田脚本への厳しい声
最新作『果てしなきスカーレット』が話題となるなか、注目を集めたのは作品そのものよりも脚本に対する手厳しいレビューでした。
Filmarksや映画.comでは「ストーリーが散漫で一貫性がない」「キャラの動機が弱くて感情移入できない」など、ストーリー面への不満が7割以上を占めています。
SNSでは公開初日から「映像はすごい。でも話が追えない」「奥寺さん戻ってきて…」という意見が増え、再タッグ待望の声がかつてない勢いで広がりました。
かつて、細田守監督と奥寺佐渡子さんがタッグを組んだ『時をかける少女』(2006)、『サマーウォーズ』(2009)はキャラクターの心情描写やストーリーの一体感で高く評価され、今なお“現代アニメの金字塔”と呼ばれています。
一方で、『バケモノの子』(2015)以降は細田監督の単独脚本が主流に。
この変化を受けて「美しいのに心に響かない」「言いたいことが伝わってこない」といった声も年々増え続けています。
擁護派からは「細田のビジョンが純粋で挑戦的」「ビジュアルで語る力がある」といった肯定的な意見も。
一方で、奥寺脚本の『国宝』が100億円を超える大ヒットとなったことで、「やっぱりこのコンビじゃないと」との期待も再び高まっています。
こうした議論の根底には「単なる批判」ではなく、「あの頃の感動を、もう一度味わいたい」というファンの切実な願いが感じられます。
なぜコンビ解消?奥寺佐渡子と組まなくなった3つの有力説
ファンの最大の疑問は「なぜ細田守は奥寺佐渡子と再びタッグを組まなくなったのか?」という点です。
ここではネットや業界の証言から、囁かれる3つの有力説を検証します。
1. 作家性の変化による「テーマの深化」
『バケモノの子』以降、細田監督の作品テーマは「家族」「成長」といった自身の体験や想いに強く傾いています。
父親になった経験が、作品の中に直接的に反映されているのが特徴です。
2018年のインタビューでも「奥寺さんに任せていた頃は楽だった。でも、いつか自分の言葉で描きたかった」と語り、「自分の作品として昇華したい」という欲求の高まりがあったことが分かります。
2. 絵コンテ先行の制作スタイルと相性の問題
細田作品は、先に映像イメージを固めていく独自の制作スタイルが特徴です。
このアプローチは、先にセリフやプロットを構築したい脚本家とは“かみ合いづらい”ことも多く、奥寺さんのような人物描写にこだわる脚本家とは衝突が生まれやすいと言われています。
現場からも「監督の頭の中にある映像が優先され、脚本の自由度が狭まる」という証言が聞かれました。
3. スケジュールやプロジェクトの不一致
奥寺佐渡子さんは近年、他の大型プロジェクトでも活躍中で、『国宝』などヒット作を連発しています。
一方で細田監督も『未来のミライ』から『スカーレット』まで短期間で新作を続けており、制作スケジュールがかぶったことでコラボが難しかった可能性も否定できません。
SNSでは「トラブルで決裂?」との噂もありますが、明確な対立や不仲を示す証拠は一切なく、むしろ細田監督は「ジブリのような純度の高い作家性」を追い求めていると語っています。
宮崎駿監督への尊敬と挑戦意識が、単独脚本へのこだわりに繋がっているという見方も根強いです。
単独脚本にこだわる理由は?細田守が目指す「純度」の代償
それでは、なぜ細田監督はここまで単独脚本にこだわるのでしょうか。
理由は明確で、「自分の内面を、他人の解釈なく描きたい」という強い信念があるためです。
とくに『未来のミライ』では、自身の子育て経験をそのまま投影し、「自分の視点でなければ描けなかった」と語っています。
この姿勢自体は尊重されるべきですが、その一方で「共感できない」「ついていけない」と感じる観客も増えつつあるのが現実です。
『竜とそばかすの姫』(2021)や『果てしなきスカーレット』でも、スケールは大きくともキャラクターの感情や物語の焦点がぼやけてしまうという指摘が多く見受けられました。
脚本に第三者の視点が加わることで、物語に普遍性や客観性が生まれるのは間違いありません。
奥寺さんとの作品には、まさにその「バランス感覚」がありました。
批評家からも「そろそろ他人の視点を取り入れては」という意見が増加し、Xでも「細田×奥寺で“ジブリ後継”復活を」といった投稿が相次いでいます。
細田監督の挑戦は高く評価されますが、それが観客との距離につながってしまうのであれば、もう一度“二人三脚”の魅力を思い出してほしいと願うファンも多いのではないでしょうか。
再タッグは本当に実現しないのか?
2025年11月、『果てしなきスカーレット』公開と同時に「なぜ奥寺さんと組まないの?」という疑問が再燃しました。
その背景には、「あの頃の名作をもう一度見たい」という純粋な願いと、「今の細田作品がもったいない」という惜しむ声が交錯しています。
もちろん、作家としての成長や「自分の言葉で描きたい」という細田監督の哲学も理解できます。
しかし、その思いを観客が共感できる形で伝えるためにも、脚本家との協業は今こそ見直すべきタイミングかもしれません。
SNSでの熱狂は一過性ではなく、今や多くのファンが「再タッグを望む理由」を理性的に語り始めています。
細田守監督が再び奥寺佐渡子さんとタッグを組む日は来るのでしょうか。
それはまだ誰にも分かりません。
ただ確かなのは、二人がかつて作り上げた物語が今なお多くの人の記憶に残り、「あの頃の映画体験」を超える新たな名作を待ち望んでいる、ということです。