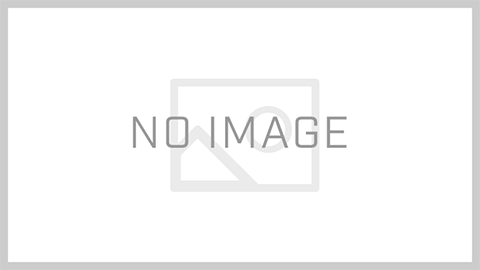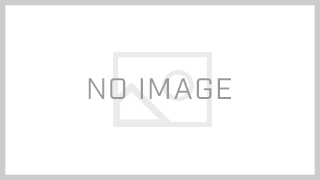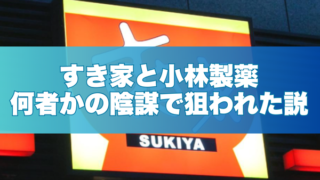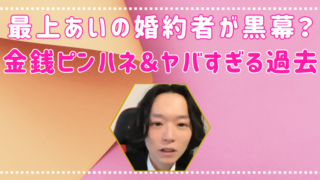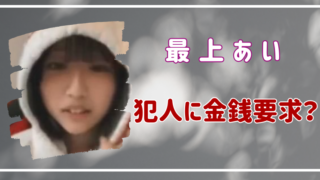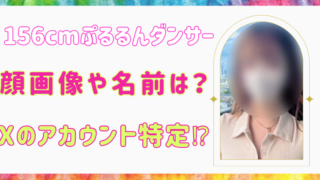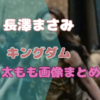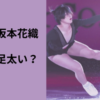熊が出没するのはメガソーラーの環境破壊が原因?再エネ政策の裏にある深い闇

最近、「熊の出没が多すぎる」と感じたことはありませんか?
地方のニュースで毎日のように流れる熊の目撃情報。
けれど、その背景を掘り下げると、単なる“ドングリ不足”や“山離れ”だけでは済まされない現実が見えてきます。
山の奥深くで起きている、ある変化。
再エネの名のもとに進む開発。
そして、語られない矛盾。
一見無関係に思える「再生可能エネルギー政策」と「熊の出没」が、実は深くつながっているとしたら……?
知られざる視点から、熊が人里に現れる“本当の理由”を考えてみませんか。
この記事では、メガソーラーと環境破壊、そして政策の裏にある構造的な問題に光を当てます。
メガソーラーと熊出没の関係とは?
「最近、熊の出没ニュース、多すぎじゃない?」
そう感じている人は多いはずです。
2023年は熊による人的被害が219人と過去最多を記録しました。
さらに、2024年も出没ペースが前年を上回っているとされ、緊張感が高まっています。
テレビでは「ドングリが不作だから」「里山が荒れてるから」とよく言われますが……それだけでしょうか?
実は今、SNS上で注目されている“もう一つの説”があります。
それが、メガソーラーによる環境破壊が熊の出没に関係しているのでは?というもの。
X(旧Twitter)でも「メガソーラー建ったら、熊が出るようになった」といった声が頻繁に見られるようになっています。
中でも奈良県平群町では、48ヘクタールもの山林を伐採してメガソーラーを建設する計画が進行。
地元住民の間では、「熊が人里に出るようになったのは、山を壊したせいでは?」という声が上がり、反対運動も起こりました。
実際、メガソーラー建設による森林伐採や生態系の破壊が全国各地で問題視されているのです。
ところが、NHKなどの大手メディアはこの仮説に慎重な姿勢。
「メガソーラーと熊の出没に直接的な関係はない」
「研究が不足しており、根拠が乏しい」などと報じられています。
うーん、たしかにデータ不足は否めない。
でも、それって“証拠がない”んじゃなくて、“まだ調べてないだけ”じゃないの?とモヤっとしますよね。
そもそも、再生可能エネルギーによる森林伐採は、日本全体の森林面積の0.08%。
一見すると小さな数字ですが、熊にとっての住処は「どこでもいい」わけじゃありません。
広葉樹林や沢沿い、水場の近くといった“限られた餌場や通り道”に依存しています。
だからこそ、局所的な伐採が大打撃になることもあるんです。
さらに、秋田県、福島県、静岡県、奈良県など、熊の出没が多い地域とメガソーラー建設地域が重なるケースもあります。
もちろん、直接的な因果関係は今後の研究に委ねられますが、地域住民の感覚として「関係あるんじゃ?」と思うのは自然なこと。
実際、Xでも「山を削っておいて、熊が出てきたら“ドングリのせい”っておかしくない?」というツッコミが多数。
市民の間では、こうした感覚が広がりつつあるのも事実です。
にもかかわらず、国やメディアは「山の開発が熊の出没に関係している可能性」について、ほとんど触れません。
それどころか、話題にすらならない。
こうなると、「メガソーラー=再生可能エネルギー=正義」という構図を守りたいのでは?」と勘ぐる声が出てくるのも無理はありません。
いま、熊がなぜ出てくるのか?
その背景には、気候や食糧の話だけでは語れない“開発と自然の衝突”があるのかもしれません。
次の章では、より具体的に「熊が人里に来るようになる環境破壊」の実態に迫っていきます。
環境破壊が熊を人里に追う理由

引用 : 岩手日報
そもそも熊って、本来は人の気配を嫌う、静かな山奥の住民です。
昼間に街に出てくるなんて、本来ありえない行動。
なのに、住宅街を歩いていたり、コンビニの防犯カメラに映っていたり……。
「いや、そこ来る?」とつい声が出るくらい異常な光景が増えています。
でも、これにはちゃんとした“背景”があるのかもしれません。
キーワードは「餌場の喪失」と「移動ルートの分断」です。
まず、熊が秋に食べる主な食べ物といえば、ドングリやクリなどの木の実。
それらを実らせるのは、ブナやミズナラといった広葉樹林です。
しかし今、その広葉樹林が全国で大規模に削られています。
2022年5月時点のデータでは、メガソーラーを含む再生可能エネルギー事業による森林伐採面積は約2.3万ヘクタールにのぼるとされています。
想像してみてください。
熊からすれば、ある日突然“ごはんの棚”が全部なくなったような状態です。
Xでも、こんな声が共感を集めていました。
北海道で新聞配達員さんが配達中ヒグマに引きずられていきお亡くなりになった
悲しいよ
今年本州まで石旅に車で行き思ったのは、ソーラーパネル北海道が一番ヤバイのでは?って恐怖
動物の住みかを奪うくらいメガソーラーだらけ
こんなんじゃ市街地に熊もおりてきますよ#自然破壊 #メガソーラー— towa ainutronica (@towaainutronica) July 12, 2025
加えて、熊の移動経路も問題です。
熊は季節に応じて、餌を探して広い範囲を移動する習性があります。
でも、そのルート上にフェンス付きのメガソーラー施設ができたら……?
「いつもの道がふさがれてる → 餌場に行けない → 仕方なく人里に下りる」
こんな流れになってしまうのも、当然といえば当然です。
実際、Xでは「熊が住宅地に現れたニュース、地図で見るとその裏山にソーラー施設がある」といった指摘も見られます。
熊が食べるのは木の実だけじゃありません。
下草、昆虫、小動物、さらにはキノコや川魚も重要な栄養源です。
でも、メガソーラーの建設現場では、土地をならすために草や土壌を根こそぎ取り除くケースがほとんど。
つまり熊にとっては、「あらゆる食材が置いてある山のスーパー」が潰れていくようなものなんです。
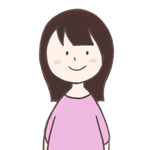
さらに、一部では環境の変化そのものが熊にストレスを与えているのでは?という指摘もあります。
たとえば、Xやネット上では「ソーラーパネルから出る電磁波が熊の行動に影響を与えているのでは?」という説も浮上しています。
もちろん科学的な裏付けはまだ不十分ですが、風力発電による低周波音が動物に影響を与える研究は存在します。
人間には感じ取れない何かが、熊を混乱させている可能性もゼロではないのです。
さらに見落とされがちなのが、メガソーラー建設の法的ハードルの低さです。
実は、メガソーラーは規模や地域によっては法的な環境アセスメント(影響調査)が不要なケースが多いんです。
風力発電のように常に義務というわけではなく、10メガワット未満ならアセスメントが免除されるケースも多々あります。
つまり、熊や他の野生動物への影響を調査しないまま山を削ってしまう……という現場が全国に存在しているということ。
熊は、何も悪くない。
変わったのは、熊じゃなくて、山のほうなんです。
Xでも「熊が悪者にされててモヤモヤする」「人間が原因で追い出してるんじゃん」といった声が目立ちます。
これはただの“動物出没ニュース”ではありません。
自然とのバランスが崩れているという静かなSOSなのかもしれません。
では、なぜメディアや政府はこの問題をもっと深く報じないのか?
次は、再エネ政策に隠された矛盾や、語られない“闇”に迫っていきます。
再エネ政策に隠された矛盾と影響
「再生可能エネルギーって、いいことなんじゃないの?」
そう思っていた人も多いはず。(私もそうでした)
地球に優しい、クリーンで持続可能、CO₂削減……。
確かに、その理念は間違っていません。
でも、その“きれいごと”の裏で何が起きているか。
そこに目を向けると、ちょっと複雑な現実が見えてくるのです。
メガソーラーの建設が全国で広がったのは、2012年の固定価格買取制度(FIT)導入が大きなきっかけでした。
電気を一定価格で買い取ってもらえる制度ができたことで、太陽光発電はビジネスとして一気に注目されるように。
「山を切り開いても利益になるならやろう」と、企業が動き出しました。
その結果、森林が削られ、斜面が崩され、野生動物の生息地も激変。
でもそれが、「再エネだから仕方ないよね」と済まされてきたんです。
では、なぜこうした影響が、メディアであまり取り上げられないのでしょうか?
ひとつの理由として、否定的な報道をすれば、国策への批判と受け取られかねないという空気があるのかもしれません。
「メガソーラーが熊の出没に関係しているのでは?」
という仮説を追いかけること自体、タブー視されがち。
Xでは、「テレビはドングリの話しかしない」「山が削られたことには一切触れない」といった声が頻繁に見られます。
本当に偶然なのでしょうか?
さらに矛盾を感じるのは、環境省の立場です。
環境保護と野生動物管理を担う一方で、再生可能エネルギー導入も支援している。
要は、「山も守りたい、でもエネルギー政策も進めたい」という、両立が難しい役割を同時に背負っているわけです。
これって、かなり無理がありますよね……。
Xでも「環境省って、結局どっちの味方?」という疑問の声が上がっています。
そして問題はもうひとつ。
秋田県や福島県など、熊の出没が多い地域とメガソーラー設置地域が重なるケースがあるにもかかわらず、その相関を本格的に調べた公的データがほとんど存在していないこと。
「調べてないのか、それとも“調べないようにしてる”のか……」
こう勘ぐりたくなるのも無理はありません。
さらに、一部のメガソーラー事業に外資が関与しているとの指摘がXで話題になっています。
「誰のために山を削ってるのか不透明」
「外資に売り渡してるようなもんじゃない?」といった声も。
もちろん全てがそうではないですが、こうした不信感が政策全体への疑念につながっています。
結局のところ、「熊が出るようになったのはドングリが不作だから」では説明しきれない。
背後には、再エネ政策の急拡大による自然破壊と、その影響を軽視してきた姿勢があるのではないでしょうか。
いま、Xなどで
「熊が出没するのはメガソーラーの環境破壊が原因では?」
と考える声が確実に増えています。
もはやこれは一部の憶測ではなく、多くの人が実感として抱き始めた疑念とも言えます。
自然と共に生きる社会を目指すはずの“再エネ政策”。
でもその裏では、熊の出没、森林伐採、地域の不安、そして無視される声……。
それらすべてが、「再エネ政策の裏にある深い闇」として、私たちの目の前に現れているのかもしれません。
私たちに今できるのは、こうした問題に目を向け、問うことです。
「本当にクリーンなエネルギーとは何なのか?」
そして、「自然との共存って、どうあるべきなのか?」
熊の出没は、その答えを私たちに問いかけているのかもしれません。