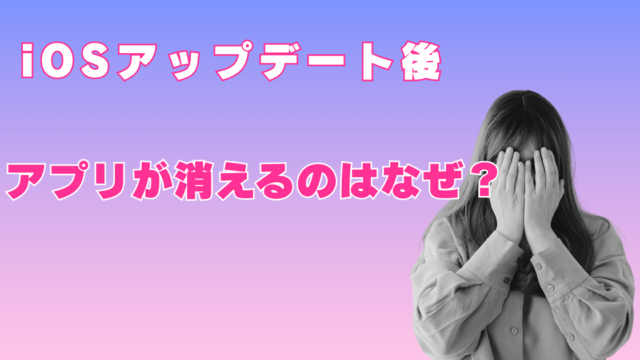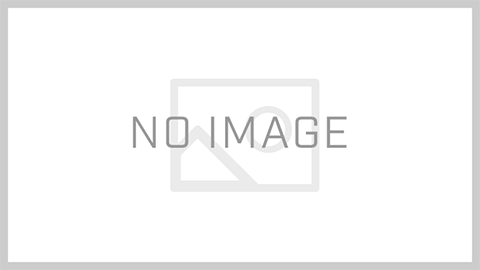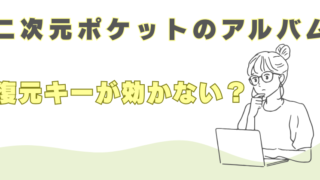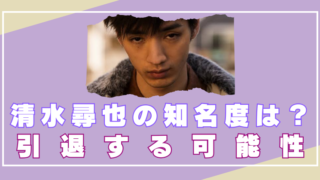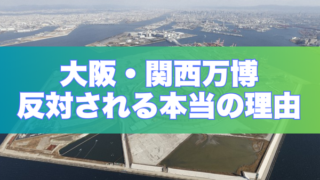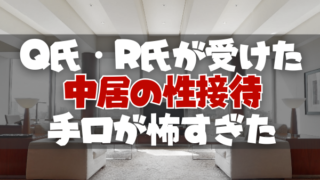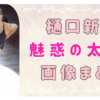三橋貴明の投資広告は詐欺?ユーチューブCMを表示させない方法
最近、YouTubeを見ていると「またこの広告か…」と感じる瞬間がある人も多いようです。
特に、三橋貴明という名前を使った“投資関連のCM”に見覚えがある方も少なくないのではないでしょうか。
動画の冒頭や合間に、「必ず上がる銘柄がある」「今すぐLINE登録で無料招待」といった文言が流れ、見るたびに不安や違和感を抱く人も増えています。
「これは本当に本人が出演しているのか?」
「なぜ自分の画面にこんな広告ばかり表示されるのか?」
この記事では、三橋貴明氏の名前を使った広告の実態と、YouTube上で繰り返し同じような広告が表示される背景を解説します。
詐欺との関連やその手口、そして被害に遭わないための注意点も含めてお伝えします。
あなたの画面に現れる広告は、実は“偶然”ではないかもしれません。
なぜ特定の広告ばかり出るのか?
「また同じような広告か…」
そんな風に感じたことがあるなら、それは気のせいではありません。
YouTubeはGoogleの広告配信システム「Google広告(旧AdWords)」を採用しており、ユーザーの行動履歴に基づいて“パーソナライズ広告”を配信しています。
つまり、
- 経済や資産形成に関する動画をよく視聴している
- 投資系チャンネルを登録している
- 関連広告や動画を過去に閲覧・クリックしたことがある
このような履歴があるユーザー層に対して、関連性の高い広告が繰り返し表示される仕組みです。
広告主は、「30代以上の男性」「副業や投資に関心のある層」など、細かいターゲット設定が可能です。
そのため、あなたがその条件に該当すれば、表示される広告は自然と似通ってきます。
この広告配信の仕組みは、個人を特定するのではなく、「似た特徴を持つグループ」に向けて効果的に届ける設計となっています。
ですから、「なぜ自分だけ…?」と感じるのは当然とも言えます。
そして一度その広告を“スキップせず視聴”したり、“クリック”しただけでも、YouTubeは「興味あり」と判断し、同種の広告がさらに増えるという“学習”も行います。
結果として、特定の広告が繰り返し効果的にあなたの画面に表示されるようになるわけです。
広告の背後には、あなたの興味・行動を分析したアルゴリズムが静かに働いているのです。
広告に本人は出ていない?
投資系の広告に登場する著名人──
それを見て「本人が出演している」と思い込んでしまう人は少なくありません。
しかし実際には、これらの広告の多くにおいて、本人が関与していないケースも確認されています。
一部の著名人は、自身の公式チャンネルやSNSで「名前や映像が無断で広告に使用されている」と警告を出していることがあります。
広告の内容によっては、本人の許可なく映像が使われているにもかかわらず、あたかも本人が勧めているように見せかけているものも存在します。
こうした状況を可能にしているのが、AIによる“ディープフェイク”技術です。
現在では、著名人の公開済み映像や音声データを元に、極めて自然な動き・口調でなりすまし動画を生成することが可能となっています。
表情の動きや声の質感も再現度が高く、一見して本物と見分けがつかないケースも少なくありません。
たとえば──
- 顔の表情をリアルに再現するフェイストラッキング技術
- 本人の声を模倣する音声合成AI
- 映像と音声を自然につなぎ合わせる編集技術
これらを組み合わせることで、まるで本人が実際に話しているような映像が生成されるのです。
こうした広告に接したユーザーは、自然に信じ込んでしまいやすく、オンライン登録やセミナーへの誘導へとつながる導線に沿って、次のステップに進んでしまうケースもあります。
また、これらの広告は海外から配信されている場合もあり、日本国内の管理者が介入しにくい点も問題視されています。
いずれにせよ、動画内に登場する“有名人の姿”は、本人の意思とは関係のない合成物である可能性があります。
「見たことある顔だから安心」
「この人が言ってるなら大丈夫」
そんな直感的な信頼は、今や通用しない時代に突入しています。
本当に本人が関与しているのか?
その情報は、正規の発信元(公式チャンネルや認証済アカウント)から発信されたものなのか?
まずはそこを確認する冷静さが、トラブルから身を守る第一歩です。
LINE登録で騙される典型的な流れ
著名人や信頼感を装った投資広告を見たあと、次のステップとして多くの人が誘導されるのが、「無料でノウハウが手に入る」といった魅力的な呼びかけです。
ここで使われる手法には、一定のパターンが見られます。
①広告で“信頼感”を与える演出
広告内には、著名人や専門家を装った映像・声が使われることがあります。
「今後確実に伸びる銘柄」
「初心者でも1日で稼げる」
など、力強い言葉とともに、安心感を与えるような演出がされています。
見慣れた顔や落ち着いた語り口によって、「この人の言うことなら信用できそうだ」と思わせる構成が多く見受けられます。
②LINEやメッセージアプリへ誘導
動画の最後には、「今すぐ登録」「無料で投資講座をプレゼント」などの文言と共に、LINEやメッセージアプリへのQRコードやリンクが提示されます。
アクセスすると、個別チャットやグループチャットに招待されるケースが一般的です。
こうしたチャットルームには、あらかじめ数名の参加者がいるように見えたり、活発な会話が交わされているような雰囲気が演出されていることもあります。
これらのチャットやグループは、詐欺グループが運営している可能性があるため注意が必要です。
③少額からの“お試し投資”を案内
チャット内では「専属コーチ」や「講師」「運用担当者」と名乗る人物が現れ、「まずは数千円から気軽に始められます」といった形で参加を促してきます。
誘導されるまま、専用の投資アプリやウェブサイトに登録し、少額の入金を行うよう勧められます。
その際には、「今のところ数千円が1万円に増えました」といった、“成功体験”のように見える画面を提示されることもあります。
ただし、こうした表示される利益は画面上の演出であり、実際の運用益ではない場合が多い点には注意が必要です。
④“今だけ”という言葉で追加投資を要求
しばらくすると、「より大きな利益を狙うなら今がチャンス」「本格的な案件には30万円の準備が必要です」などといった言葉で、さらに大きな金額を投資するよう求められます。
この時点で心理的に「もう引けない」「ここまで来たら信じたい」と思ってしまう人も少なくありません。
加えて、他の参加者が「自分も参加しました」「今入金しました」と発言することで、集団心理を利用した“安心感”を演出する手口も見られます。
⑤出金できない→音信不通に
最終的に「利益が出ました」「出金できます」と案内されても、実際には様々な理由で出金できないケースが目立ちます。
- 「口座の確認に手数料が必要」
- 「税務処理のために先に入金してください」
- 「システム上の問題で一時的に停止中」
このような理由で、さらに追加の送金を要求されたあと、急に連絡が取れなくなる、ログインできなくなるなどの被害が報告されています。
この時点で送金したお金は、取り戻すことが極めて困難です。
このような一連の流れは、信頼感を悪用した投資詐欺の典型的なパターンとして、多くのケースで共通しています。
「少額だから大丈夫」
「みんなやってるから平気」
という油断こそが、詐欺の入口になり得るのです。
たとえ魅力的に見えるオファーであっても、オンラインでの登録や送金を伴う案件には冷静に対処する意識が不可欠です。
しつこい広告を表示させないための対処法
「なぜこの広告ばかり何度も出てくるのか…」
そう感じたことがある方にとって、繰り返し表示される広告はストレスの原因になりかねません。
youtubeの広告で最近流れる三橋貴明とかいうおっさんの株だか投資だかの広告が真面目にうざすぎる
ブロックしてもブロックしても何度もでてくる
こっちは投資もFXも信託何もしてないんだよ!
映像も声も話してる内容もウザすぎてきつい、きつすぎる pic.twitter.com/9y4IgX6hqx— コヒキチa.k.a.ちょび丸🐶🎈 (@kohikiti210li) September 1, 2025
YouTubeやGoogleの広告表示にはアルゴリズムが関わっており、ユーザーの過去の行動履歴をもとに広告が最適化される仕組みがあります。
そのため、同じジャンルの広告が頻繁に出てくることがあります。
ここでは、不要な広告が表示されにくくなるための具体的な対処法を紹介します。
① 「この広告に興味がない」とフィードバックする
YouTubeの広告右上の「i」マークや「︙」メニューから、「この広告を表示しない」「興味がありません」などを選択できます。
これにより、同様のカテゴリや広告主の広告が表示されにくくなる傾向があります。
② Googleアカウントの広告設定を見直す
Googleでは「広告設定」ページを通じて、自分に表示される広告の種類や興味関心の推定を確認・変更できます。
- 表示されている興味カテゴリを削除
- パーソナライズ広告をオフに切り替え
などの操作が可能です。
→ Google広告設定ページ(https://adsettings.google.com)
③ 閲覧・視聴履歴を定期的にリセットする
YouTubeやGoogleでは、検索履歴・視聴履歴・クリック履歴などが広告配信のターゲティングに影響します。
そのため、投資系のコンテンツを一度見ただけでも、関連する広告が増えることがあります。
- YouTubeの「履歴とプライバシー」から視聴履歴を削除
- Googleの「マイアクティビティ」で広告に関連するデータを削除
- 広告に関連するデータ収集を制限または削除
これにより、関心のない広告が表示される頻度を抑えることができます。
④ YouTube Premiumの利用も選択肢に
どうしても広告を見たくない場合、有料プランであるYouTube Premiumの利用を検討するのも一つの方法です。
月額料金(例:日本では1,180円〜)がかかりますが、
- 広告なしで動画視聴が可能
- バックグラウンド再生やオフライン視聴が利用できる
といった利点があり、快適にコンテンツを楽しみたい人には有効な選択肢です。
⑤ あやしい広告は“通報”でブロック
「怪しい」「誤解を招く表現だ」と感じた広告は、無視せずに通報しましょう。
YouTubeやGoogleの広告では、「広告の報告」オプションから不適切な内容を通知できます。
個々のアクションが、広告の不適切な配信を減らすのに役立つ場合があります。
見過ごさず、少しの手間で対処することで、安全な広告環境づくりに貢献できます。
まとめ
広告は本来、情報を届けるためのツールですが、悪質なケースでは、不安をあおられ、金銭的なリスクが生じる可能性があります。
特定の広告が何度も表示される背景には、ユーザーの過去の行動や広告主の設定が絡んでおり、偶然ではありません。
こうした仕組みを理解することで、無駄に不安を感じることなく冷静に対処できるようになります。
そして何より大切なのは、「本当に信頼できる情報か?」と一度立ち止まって確認する視点です。
広告や発信内容に違和感を覚えたら、公式情報や信頼できるソースを参照する習慣を持ちましょう。
それが、あなた自身の時間とお金、そして安心を守る最も確実な手段です。